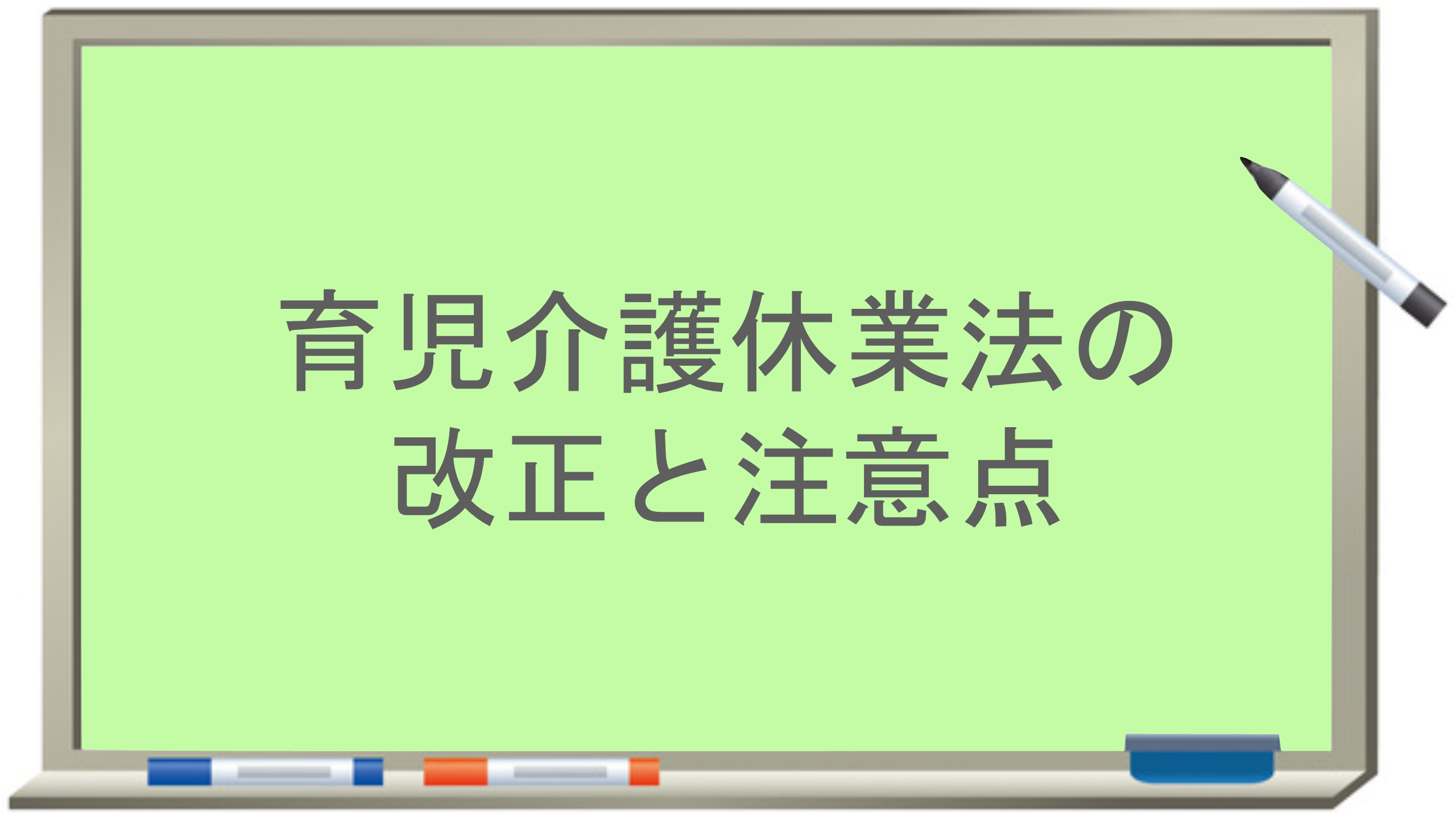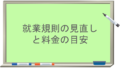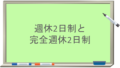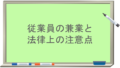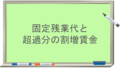東海地方の田舎町で【コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
本日から4月となりましたが、労務管理の部分では本日から育児介護休業法が順次改正されることになっています。
従業員規模が増えてくると育児介護休業を取得する従業員も増えてきますし、労働力不足が深刻な状況においても従業員の確保は重要な課題となると感じています。
さて、今回は育児介護休業法の改正と注意点を以下の3点にまとめました。
- 休みに関する変更
- 労働時間に関する変更
- 対象者に関する変更
休みに関する変更
子の看護休暇
子の看護休暇を取得できる制度は元々ありました。
4月からは「子の看護等休暇」という名称に変わり、子どもの範囲や取得するための理由が増えます。
まず、対象となる子どもですが、小学校に入学するまでの子どもから、小学校3年生の年度末までの子どもが対象と変わります。
また、理由も感染症による学級閉鎖や入園式と卒園式でも休暇を取得することができるようになります。
| 改正内容 | 施工前 | 施工後 |
| 対象となる子の範囲の拡大 | 小学校就学が始まるまで | 小学校3年生修了まで |
| 取得事由の拡大 | ①病気・ケガ ②予防接種・健康診断 | ①病気・ケガ ②予防接種・健康診断 ③感染症に伴う学級閉鎖 ④入園(入学)式、卒園式 |
取得状況の公表
取得状況の公表は、以前は1,000人を超える従業員を雇用している規模だったところが、300人を超える従業員を雇用している規模になります。
300人以上でも十分大きな企業であると言えますが、今までよりも対象となる企業が増えることで、将来を見据えた就職活動にも役立つのではないかと考えられます。
長い目でキャリアを築いていきたい労働者を採用したいと考えている企業は、公表することのメリットを良く把握しておくとよいです。
| 改正内容 | 施工前 | 施工後 |
| 公表義務の企業規模 | 従業員数1,000人超え | 従業員数300人超え |
労働時間に関する変更
残業免除の対象拡大
幼い子を養育している労働者は以前から時間外労働を制限されていました。
今回の改正で小学校就学前のお子さんを養育している人にまで拡大されたのも大きなポイントとなります。
約3年間の残業を免除される期間が延長しますので、子育てにより多くの時間を割くことができるようになります。
| 改正内容 | 施工前 | 施工後 |
| 請求可能となる労働者の範囲拡大 | 3歳未満の子を養育する労働者 | 小学校就学前の子を養育する労働者 |
短時間勤務制度の拡充
出産を機に、短時間勤務に切り替えている労働者の方もいます。
始業時間を繰り下げたりするという方法に加え、テレワークという働き方も選べるようにすることができるようになりました。
短時間勤務制度ができる場合は、そちらを採用しなければなりませんのでご注意ください。
| 改正内容 | 施工前 | 施工後 |
| 代替措置のメニューを追加 | 代替措置 ①育児休業制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更 | 代替措置 ①育児休業制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更 ③テレワーク |
対象者に関する変更
取得可能な労働者
以前は、育児休暇や介護休暇を取得できる労働者から継続雇用期間6か月未満の労働者を除外することができました。
ただし、今回の改正で、継続雇用6か月未満の労働者であっても除外することができなくなりました。
週所定労働時間が2日以内の場合は引き続き除外ができます。
労使協定の締結が必要ですのでご注意ください。
| 改正内容 | 施工前 | 施工後 |
| 育児休暇、介護休暇 労使協定による除外規定の廃止 | 除外できる労働者 ①週所定労働日数2日以下 ②継続雇用6か月未満 | 除外できる労働者 ①週所定労働日数2日以下 |
介護離職防止のための措置
身近な親族の介護は誰にでも起こる可能性があります。
介護をきっかけにする離職を防止できるよう、研修や相談体制を整備することで、積極的に介護と仕事の両立できる制度を使用してもらえるようにしていくことが求められます。
また、介護を必要としている状況になった労働者に対しての意向確認はもちろんのこと、介護が増えてくる前の40歳前後で制度の説明や情報提供を行うことも必要となります。
| 改正内容 | 周知事項 |
| 雇用環境整備 | ① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施 ② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置) ③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供 ④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知 |
| 個別の周知、意向確認 | ①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) ③介護休業給付金に関すること |
終わりに一言
今回の法改正では、育児や介護による離職を減らして、長く働くことができるような企業になっていくことが求められるような変更が多くあります。
半年後の2025年10月1日からは「柔軟な働き方を実現」するための措置が義務化されますが、その話はまたの機会にまとめたいと思います。
今回ご紹介した内容は、すべてが義務となっていますし、内容によっては就業規則の変更も必要となります。対応できているか不安な方は、専門家の社労士にチェックを依頼されてみることをおすすめします。弊所では、就業規則のチェックだけでなく、今回ご紹介した育休などに関わる助成金のご提案も行っております。気になる方はお気軽にお問い合わせください。