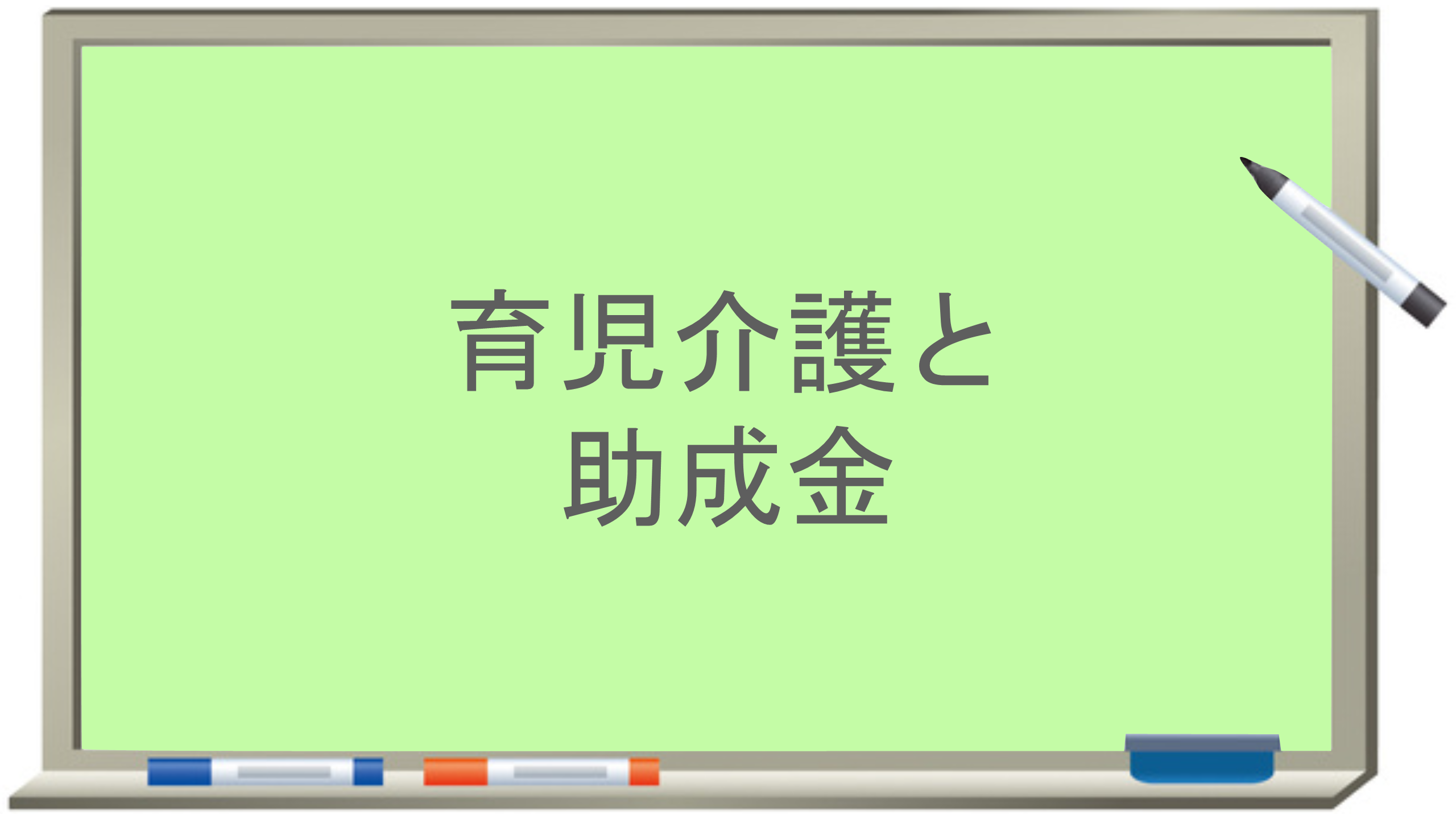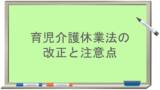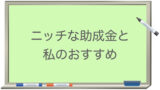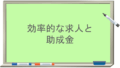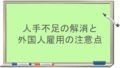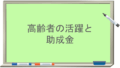東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社労士・コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
仕事と子育てや介護の両立は一定の年齢以上になると顕在化してきやすくなります。
事業所から問い合わせをいただくこともありますが、周りでもそのような悩みを抱える方が増えてきているように感じます。
また、2025年4月から育児介護休業法が改正されたこともあり、注目されやすい内容かと思われます。
さて、今回は育児や介護に関わる休業と助成金について以下の3点にまとめました。
- 育児介護休業法改正のポイント
- 受給できる助成金
- 就業規則への対応
育児介護休業法改正のポイント
2025年4月1日から施行
育児介護休業法は改正が多い印象のある法律です。
受験生時代は法改正を追うのが大変に感じていましたが、今となっては、なぜ変わるのだろう、今のままではどのような不都合があるのだろう、どのような未来を目指しているのだろう、という視点で見るようになり、印象が変わりました。
今回の改正では、休みの理由や労働時間、対象の労働者に関して改正されています。
・育児休暇の取得事由に感染症や入卒園が追加
・残業免除の対象者が小学校入学前までに延長
・除外できる労働者から6か月未満を削除
今まで以上に、育児介護休業や育児介護休暇が取得しやすくなり、仕事との両立ができる人が増えてくるのではと期待しています。
育介休法の改正について、詳しくはこちらの記事でご紹介していますので、興味がある方はこちらもご覧ください。
関連する助成金
両立支援等助成金
両立支援等助成金という助成金は出産や育児、介護に関わる制度を整備して、仕事との両立ができるような職場環境づくりをする事業主のための助成金です。
| 出生時両立支援コース (子育てパパ支援助成金) | 育児休業を取得しやすい環境整備をし、男性労働者の育児休業を取得した場合 | 【育児休業取得】 1人目:20万円 2人目3人目:10万円 【育休取得率上昇】 60万円 |
| 介護離職防止支援コース | 労働者の円滑な介護休業の取得や職場復帰に取り組み、介護休業や両立支援の制度を利用した場合 | 【介護休業】 40万円 【両立支援制度】 20万円 |
| 育児休業等支援コース | 労働者の円滑な育児休業の取得や職場復帰に取り組み、育児休業を取得した場合 | 【育休取得時】 30万円 【職場復帰時】 30万円 |
| 育児休業等業務代替者支援コース | 育休取得者や育児による短時間勤務制度の利用者の業務を代替する労働者への手当支給や、代替要員の新規採用を行った場合 | 【手当支給】 最大140万円 【新規雇用】 最大67.5万円 |
| 柔軟な働き方選択制度等支援コース | 育児中の労働者が利用できる柔軟な働き方に関する制度を複数導入して、対象労働者が制度を利用した場合 | 2つ以上:20万円 3つ以上:25万円 |
| 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース | 不妊治療のために利用可能な制度を利用しやすい環境を整備し、不妊治療に対する制度を労働者が利用した場合 | 30万円 |
このように、複数のコースが用意されており、対象となる事業所も多くあると思います。
ただ、あまりメジャーではない助成金であること、制度の整備だけではなく利用者が出てきたときに助成の対象となるため目先のお金にならないことから、問い合わせはほとんど受けたことがありません。
ただ、妊娠や介護となることが発覚してから、休業に入るまでにはそこまで長い時間は残されていないことがほとんどです。
先々を見据えて制度を用意しておくことや、制度を用意しておくことで求職者にとって魅力的な職場としていけるようにしておくことも必要ではないでしょうか。
過去の記事では、両立支援等助成金の内容だけではないですが、私のおすすめの助成金としてご紹介をしたことがありますので、あわせてご覧いただけると嬉しいです。
就業規則への対応
改正点は要修正
今回の改正では、前述の内容が4月1日から、さらに10月1日から柔軟な働き方の実現のための措置を講じる必要が出てきます。
名称が「子の看護休暇」から「子の看護休暇等」に変わる程度であれば就業規則までは必要ないかもしれませんが、取得事由の追加や対象の年齢あたりは修正しておいた方が良いかもしれません。と言いますのも、就業規則がある事業所というのは、何か起きたときには就業規則を見て判断するのではと考えているからです。
就業規則は社内のルールブックのようなものですので、社長や人事担当者だけが把握していればよいものではなく、すべての人が分かるようにしておく必要があります。
そして、労働者がいつでも自由に見ることができるようなっているはずですので、自由に見て勝手に判断することも起こり得ます。
また、義務化された内容があっても、就業規則に書かれていなければ忘れてしまう可能性もあります。
修正を依頼するとお金がかかることがほとんどですが、正しく運用していくためには必要経費だと考えていただければと思っています。
終わりに一言
顧問先となる会社はもちろんですが、就業規則のスポットのご依頼を受けるときなどに過去の就業規則に目を通すことがあります。内容が古いままのことはよくありますし、実態に即していない内容のものもあります。
定期的に修正をすることはもちろんですが、今回のような助成金も上手に活用しつつ業務に役立てていただければと思います。
顧問先以外でも就業規則の修正は承っておりますし、助成金のお話はお受けできるか分かりませんが、ご相談には乗れます。気になることがありましたら、お気軽にお問い合わせください。