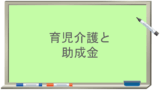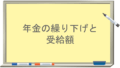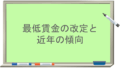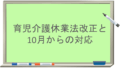東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社労士・コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
最近よくお問い合わせを受ける内容の一つに従業員の妊娠があります。
産休や育休を取得する時期、代わりの人員の採用など、考えることが多くなり時間を取られてしまうのではと感じています。
そして、妊娠初期のつわりによる欠勤をどうするのかということもよく相談されます。
さて、今回は病気やケガによる欠勤と傷病手当金について以下の3点にまとめました。
- 傷病手当金の仕組み
- 傷病手当金でもらえる額
- 遅刻や早退はどうなるか
傷病手当金の仕組み
健康保険の制度の一つ
傷病手当金は協会けんぽや健康保険組合の健康保険に加入している人が利用することができる制度の一つです。
仕事中ではない時の病気やケガで仕事を休むと、給料は減額されて支払われることになります。
事業主の視点から見ると、【ノーワークノーペイの原則】、つまり働いていない時間に対しては賃金を支払う必要はないということに従って対応しても良いということになります。
しかし、労働者も積極的に痛い思いをして病気になったりケガをするわけではないと思います。
私生活の中でも病気になったりケガをしてしまうことがあるので、その時の欠勤は健康保険の中で面倒をみていきましょうというものが傷病手当金の制度となっています。
もらうための要件
傷病手当金をもらうためには大きく4つの要件があります。
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと
これら4つの要件を満たしているときに傷病手当金をもらうことができます。
病院に行っている日だけが対象ではありませんので、自宅で療養している日も対象となります。
ただし、連続した3日間を含む休みというところがありますので、1日だけ休んだからといってもらえるわけではない点には注意が必要です。
連続した3日間の休みのことを待期期間と言いますが、少しややこしいところがあります。
連続して3日間の休みがあれば待期期間は完成します。同じ病気であれば、待期期間は一度完成していれば大丈夫です。
そしてその待期期間には、公休日や有休休暇も含めることができます。
2日間の公休日と1日の有給を組み合わせても待期期間は完成するということも言えます。
冒頭に出てきた病気やケガの一つには妊娠によるものが含まれていますので、つわりで欠勤が続いているときにはもらうことができます。
傷病手当金でもらえる額
1日分の3分の2
もらえる額がいくらになるのかということも気になる点です。
これは決められた計算式がありますので、計算式に当てはめて日額を出します。
1日あたりの金額=直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2
具体的にいくらになるのかを計算してみます。
例)
平均の標準報酬月額が30万円の場合
30万円÷30日×3分の2=6,666円
1日にすると少なく感じるかもしれませんが、30日分もらえば約20万円となりますので、生活を維持することはできる額となります。
もう一つ気になる点として、どのくらいの期間もらえるのかということになります。
同じ病気では通算して1年6ヶ月間もらうことができます。
これは、以前は休み始めてから1年6ヶ月間だったところが、最近の法改正で傷病手当金の受給をした期間を通算してに変わりました。
心の病気などの場合は無理せず、休んで体調を戻すことに専念する方が良いのではと思います。
遅刻や早退はどうなるか
待期期間の初日にはなる
ある日、体調が悪くなり早退して、翌日以降も体調がよくならずその後に数日間の欠勤を続けたとします。
そのような場合の早退の日は待期期間を計算するときの1日目として数えることができます。
ここでは、病気やケガが原因の欠勤と、通常通り勤務している日が混ざっている場合の遅刻や早退についても触れておきます。
仕事に対する責任感や、どうしも抜けることができない事情があって、短時間でも働くこともあるかもしれません。
ただ、その場合は傷病手当金を受け取ることができない日となってしまうことに注意が必要です。
短時間だけ働いて帰るということをするのであれば、いっそのこと丸一日休養して、体力の回復に努める方が色々とよいのではと考えています。
もちろん、一人分の抜けた穴をカバーするために他の人員が必要になることもありますし、残された従業員さんの負担が増えるということも分かります。
欠勤の原因が妊娠ということであれば、両立支援助成金というものもありますのでご活用いただくと、会社と残された従業員さま、休んでいる従業員さまの全員対してメリットがあります。
両立支援助成金についてのことは下記の記事で取り上げていますので、ご興味がある方はご一読いただけると幸いです。
終わりに一言
晩婚化や少子化が進む中、妊娠や出産を迎えることができるのは社会にとっても嬉しいことです。
男性の育休や子育て参画も増えてきていますが、妊娠をすることができるのは女性だけとなるため、妊娠に関わる体調不良や働けない期間が生まれるのも女性ならではの事情となってしまうのかなと感じています。
欠勤してはダメではなく、公的な支援が得られるんだということをもっと多くの方に知ってもらえたらよいなと思いました。
事業主の方や人事の方だけでなく、個人の方からのご相談を受けることもありますので、気になることがある方はお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。