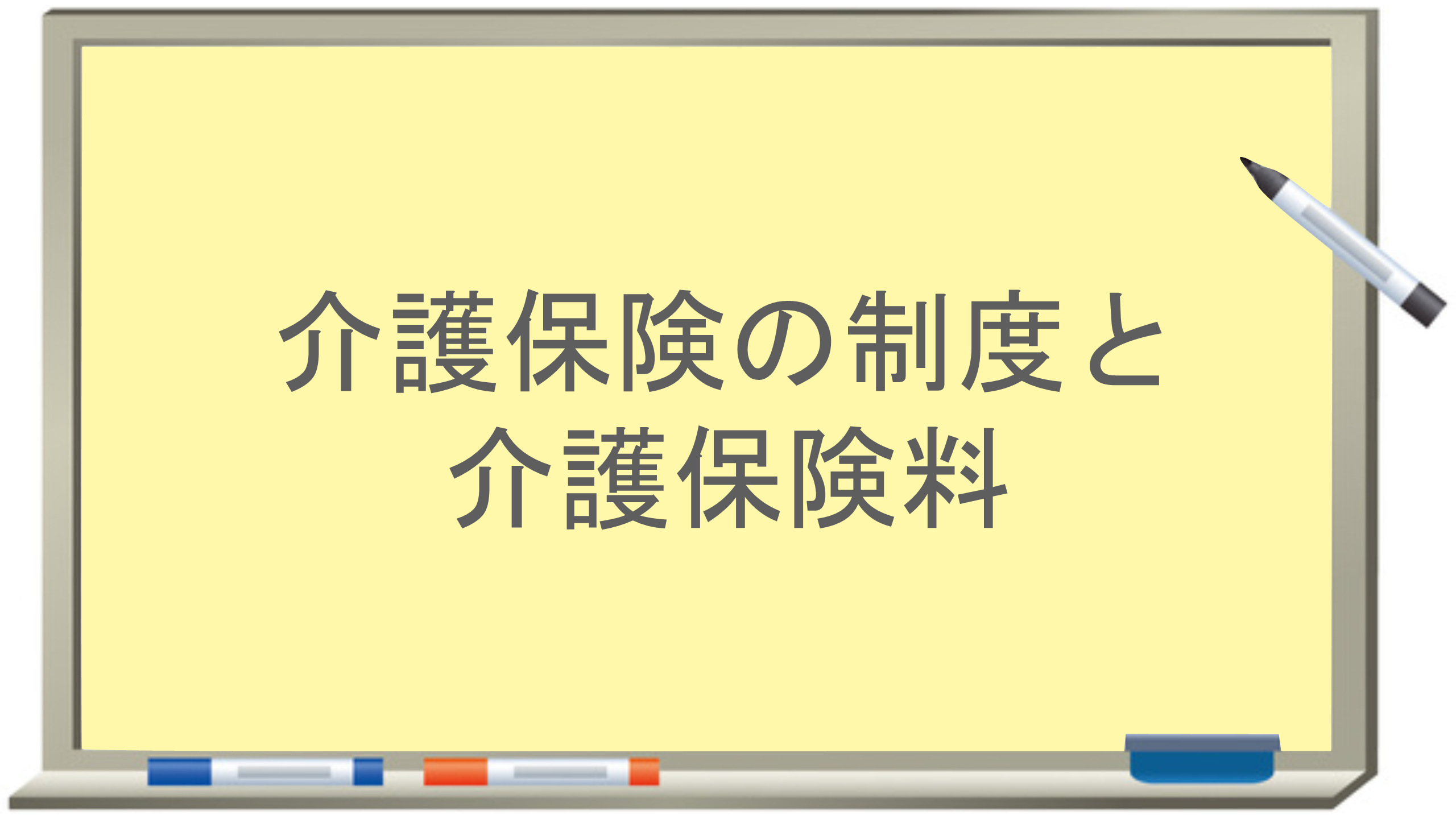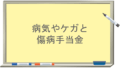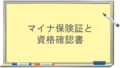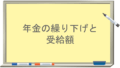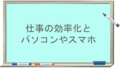東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社労士・コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
ちょうど私たちくらいの年齢から話題に上がりやすいのが介護保険です。
最近も、介護保険に関する問い合わせを受けたため調べてみたことをまとめてみます。
さて、今回は介護保険について以下の3点にまとめました。
- 介護保険の制度とは
- 介護保険料の金額
- 介護保険で受けれるサービス
介護保険の制度とは
介護が受けれる保険の一つ
介護保険とは、40歳以上になるとお給料から天引きされますので、40歳以上の方であれば見たことや聞いたことがあるかもしれません。
しかし、30代以下の方は引かれることもありませんので、気にして調べている方以外は知らない場合が多いことでしょう。
では、どんな制度なのかをまとめて見たいと思います。
介護と言えば、昔は自分や配偶者の両親などの家族に対して行うことが多かったですが、近年の高齢化が進むにつれて、介護を必要とする方も介護をしなければならない方もが高齢者という、いわゆる「老々介護」という問題が顕在してきています。
2000年に新しく始まった介護保険制度では、介護を社会全体で支える仕組みにすることで、家族の負担を軽減しています。
対象となるのは前述で天引きされているという話で出てきた40歳からとなります。
これは、40歳を超えると自分自身も老化が原因の病気で介護が必要となることが増えてくる時期ということで、40歳以上になったら介護保険料の負担が始まることになりました。
対象となる年齢や受給要件をまとめると以下のようになります。
| 65歳以上(第1号被保険者) | 40歳以上(第2号被保険者) | |
| 対象者 | 65歳以上の方 | 40歳以上64歳未満の医療保険加入者 |
| 受給要件 | 要介護状態 要支援状態 | 老化に起因する病気※によって要介護状態 |
| 保険料の徴収方法 | 市町村などが年金から天引き 65歳になった月から徴収開始 | 医療保険料と一緒に徴収 40歳になった月から徴収開始 |
※印が特定疾病というものになります。
がんや脳血管疾患など、16種類の病気が具体的に決められています。
保険料の徴収方法の欄に、40歳になったらや65歳になったらという表記があります。
40歳になるときには、なった日の属する月の給与から天引きを開始すれば問題ありません。
64歳から65歳になるタイミングでは、65歳になった日の属する月の分から市町村に納めることになりますので、今まで通り引いてしまわないように気を付けなければなりません。
なお、保険には被保険者と保険者というものがありますが、介護保険の保険者は市町村や広域連合になります。
介護保険サービスを受ける場合は介護サービス事業者に費用を負担しますが、その費用を国、都道府県、市町村、第1号被保険者、第2号被保険者で負担する仕組みとなっています。
介護保険料の金額
65歳以上
介護保険料の金額は、前年の所得に応じて決まる16の段階のどこに当てはまるかによって決まります。
年間の年金額が18万円以上の方は年金から介護保険料が天引きされることになります。
以下の表は令和6年度の美濃加茂市の介護保険料額をまとめたものになります。
| 段階 | 対象者 | 年額 |
| 第1段階~第3段階 | 世帯全員が非課税世帯 所得によって段階が異なる | 19,150円~46,030円 |
| 第4段階~第5段階 | 本人が非課税世帯 世帯の中に課税対象者がいる 所得によって段階が異なる | 57,120円~67,200円 |
| 第6段階~第16段階 | 本人が課税対象者 所得によって段階が異なる | 73,920円~181,440円 |
参照:美濃加茂市 介護保険料
40歳以上
40歳以上で介護保険の対象となる方の多くは、会社に勤めているなど仕事をしている方だと思います。
その場合の保険料は、標準報酬月額という毎月の給与から決まる額に、医療保険の定める保険料率である1.59%をかけた金額となります。(令和7年度)
健康保険や厚生年金などの他の社会保険と同じように、会社が半分負担してくれていますので、負担としてはそこまで大きいものではなありません。
介護保険で受けれるサービス
1割負担の現物給付
介護保険は介護を社会全体で支える仕組みとなっていますので、負担は少ない一方で、サービスは充実しています。
以下に介護保険で受けることができるサービスをまとめました。
| 自宅で利用するサービス | 訪問介護 訪問介護 福祉用具貸与 |
| 日帰りで施設を利用するサービス | 通所介護(デイサービス) 通所リハビリテーション(デイケア) |
| 宿泊するサービス | 短期入所生活介護(ショートステイ) |
| 居住系サービス | 特定施設入居者生活介護 |
| 施設系サービス | 特別養護老人ホーム |
| 小規模多機能型居宅介護 | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
非常に多くの、充実したサービスが対象となっていることが分かります。
これらのサービスを原則1割の負担で受けることができるのが介護保険となります。
これらのサービスは誰でも受けることができるわけではなく、「介護を必要としている状態」であるということを市町村に認定してもらう必要があります。
本人やその家族から市町村に申請を出し、訪問調査や主治医からの意見を聞くなどして本当に介護を必要としているのかを判定します。その上で市町村が認定するという流れとなります。
このように充実したサービスを受けることができる制度ではありますが、その分費用がふくらんできます。
前述で費用の負担をお伝えしましたが、大きく以下のような割合で負担しています。
社会全体で支える仕組みとなっていることを表している費用配分となっているように見えます。
| 保険者 | 負担割合 |
| 国 | 25% |
| 都道府県 | 12.5% |
| 市町村 | 12.5% |
| 第1号被保険者 | 22% |
| 第2号被保険者 | 28% |
終わりに一言
介護をきっかけとした離職の防止や、要介護状態にならない健康の維持など、本人だけでなく会社や家族も一緒に取り組んでいかなければならないことだと考えます。