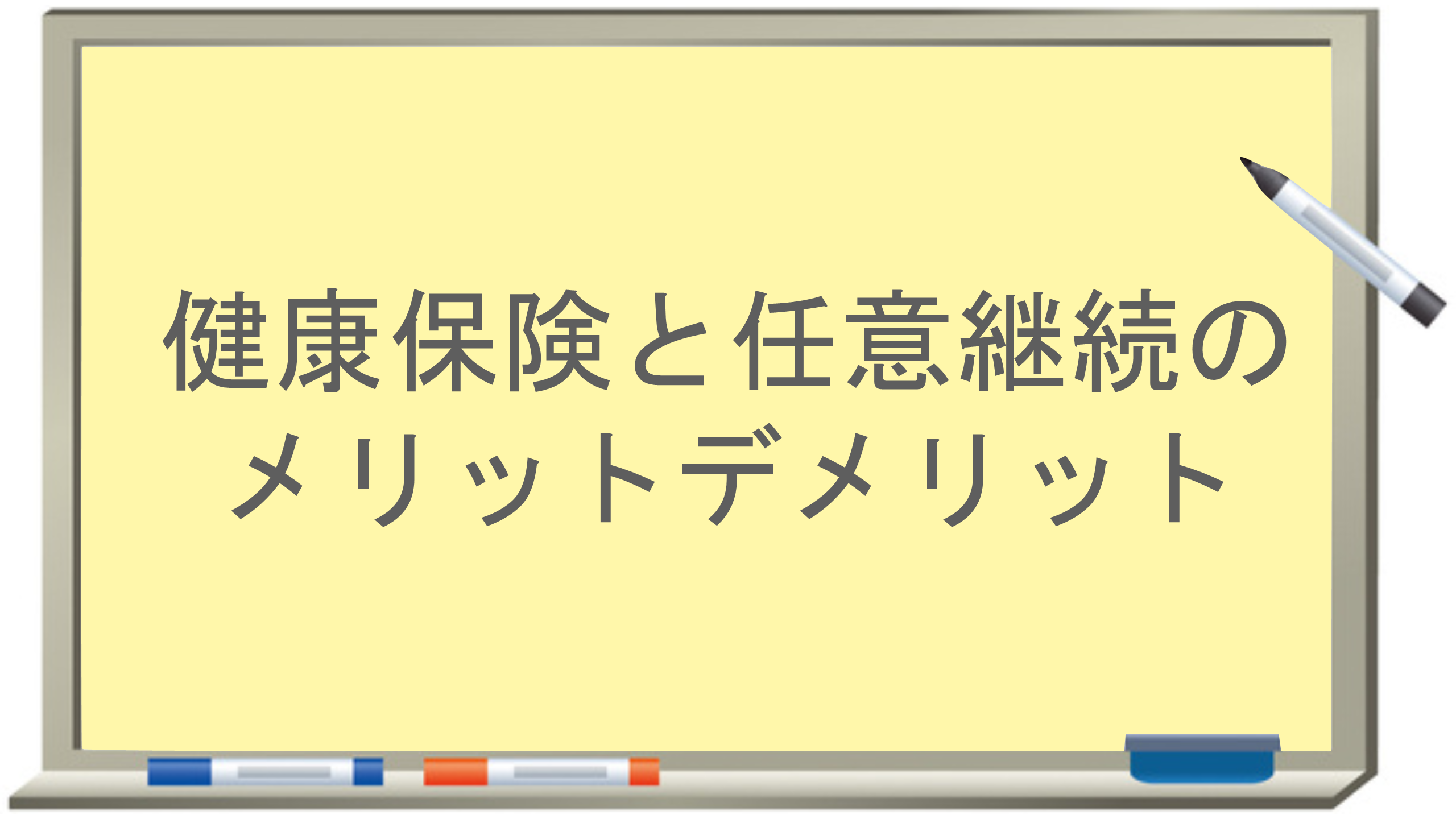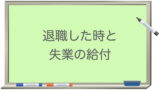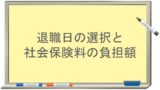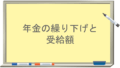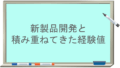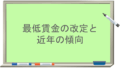東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社労士・コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
転職が当たり前の時代となり、退職の手続きをすることも多くあります。
退職したあとにどうされるのかまでは関与していませんので詳しくは存じ上げませんが、人によっては次が決まっている方から失業保険をもらいつつ仕事を探すという方もいらっしゃることでしょう。
今回は次の職に就くまでの期間が空いてしまった時の健康保険の制度について確認してみたいと思います。
退職する可能性がある労働者だけでなく、従業員を雇用している事業主様もご質問を受けたときの参考になるかと思います。
さて、今回は退職後の健康保険の制度について以下の3点にまとめました。
- 選択肢は大きく3つ
- 任意継続の制度とは
- 任意継続のメリットデメリット
選択肢は大きく3つ
国民健康保険に加入する
日本では国民皆保険となっておりますので、会社員は協会けんぽや健康保険組合に加入していますが、退職後や個人事業主は国民健康保険に加入することで、全員がなんらかの保険制度に加入することが義務付けられています。
ということで、会社員でなくなったときに選択肢の一つになるのは国民健康保険です。
国民健康保険は個人事業主などの自営業者やフリーランス、無職の方を対象としている保険制度で、保険者は各地方自治体です。
加入の手続きは、各地方自治体の役所に行って確認しておきましょう。
今の健康保険を任意継続する
そして、国民健康保険に加入しない場合の選択肢が今の健康保険の任意継続という制度になります。
退職前や退職直後であればこちらを選ぶこともできますので、お考えであれば事前にしっかりと調べて準備をしておきましょう。
なお、退職後に失業保険を受け取る予定の方は下記の記事で触れていますので、お読みいただければ幸いです。
また、退職にあたっては、退職日によって保険料の負担額が変わってくることに注意が必要です。こちらに関しては下記の記事で触れていますので、合わせてお読みいただけると幸いです。
配偶者の扶養に入る
配偶者の方が協会けんぽなどの健康保険制度に加入している場合、配偶者の扶養に入るという選択肢もあります。
税法上の扶養親族に該当するのであれば加入自体は難しいものではありませんので、そちらをご検討されても良いでしょう。
任意継続の制度とは
キーワードは「2」
任意継続という制度は、前職を退職するときに案内をもらって初めて知りました。
そのときはよく分かっていませんでしたが、後々勉強をすることでようやく理解することができました。
任意継続とは、会社を退職したあとも「一定期間、今までの健康保険の制度を継続できるという制度」になります。
キーワードとなる2が出てくる箇所は加入していた被保険者の期間、申出の期限、加入できる期間の3カ所になります。
| 加入期間 | 2ヶ月以上 |
| 申出期限 | 20日以内 |
| 加入期間 | 最長2年間 |
任意継続のメリットデメリット
メリット
メリットは
・今までの保険内容をそのまま引き継ぐことができる
・扶養家族がいる場合もそのまま扶養となることができる
・退職1年目は国民健康保険より安くなることがある
同じ世帯の人数や総所得によって、メリットが大きい人とそうでない人がいらっしゃるかと思います。
国民健康保険の保険料がいくらになるのかは、役所に行けば計算してくれることもあります。前述の通り、退職からの日数がそこまで長くありませんので、お早めに確認をしておくことをおすすめします。
デメリット
デメリットは
・保険料の全額が自己負担となる
・申出の期間が20日間しかない
・2年後には別の保険制度に加入する必要がある
全額が自己負担はデメリットのようにも見えますが、実際に計算をしてもらうと1年目は国民健康保険より安くなることもあります。
そして、2年後には別の保険制度に加入する必要があるという点ですが、自営業になる人や2年間以上無職でいることができる人は別ですが、次の就職先で保険制度に加入するのであれば特にデメリットにはならないようにも感じます。
以前は、任意継続は自分の意思でやめることができないというデメリットもありましたが、法改正でなくなっています。
そうなると、一番のデメリットは申出の期間がとても短いという点ではないでしょうか。
退職後すぐに転職はせず、残った有給を消化しているなどで時間がある場合は、役所で保険料の確認をするなどして、方向性を考えておいた方が良いでしょう。
なお、退職に伴って収入が減少する場合、2年目以降は国民健康保険の方が保険料が安くなることもあります。何事も、一度決めたら終わりではなく、定期的な見直しをした方が良いということです。
終わりに一言
退職後には、任意継続、国民健康保険、扶養に入るなどの選択肢があることが分かりました。それぞれのメリットとデメリットを考えた上でどうするかを決めていけると良いでしょう。
従業員からの質問や相談があったときや、労務トラブルが起きてしまいましたら、相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。