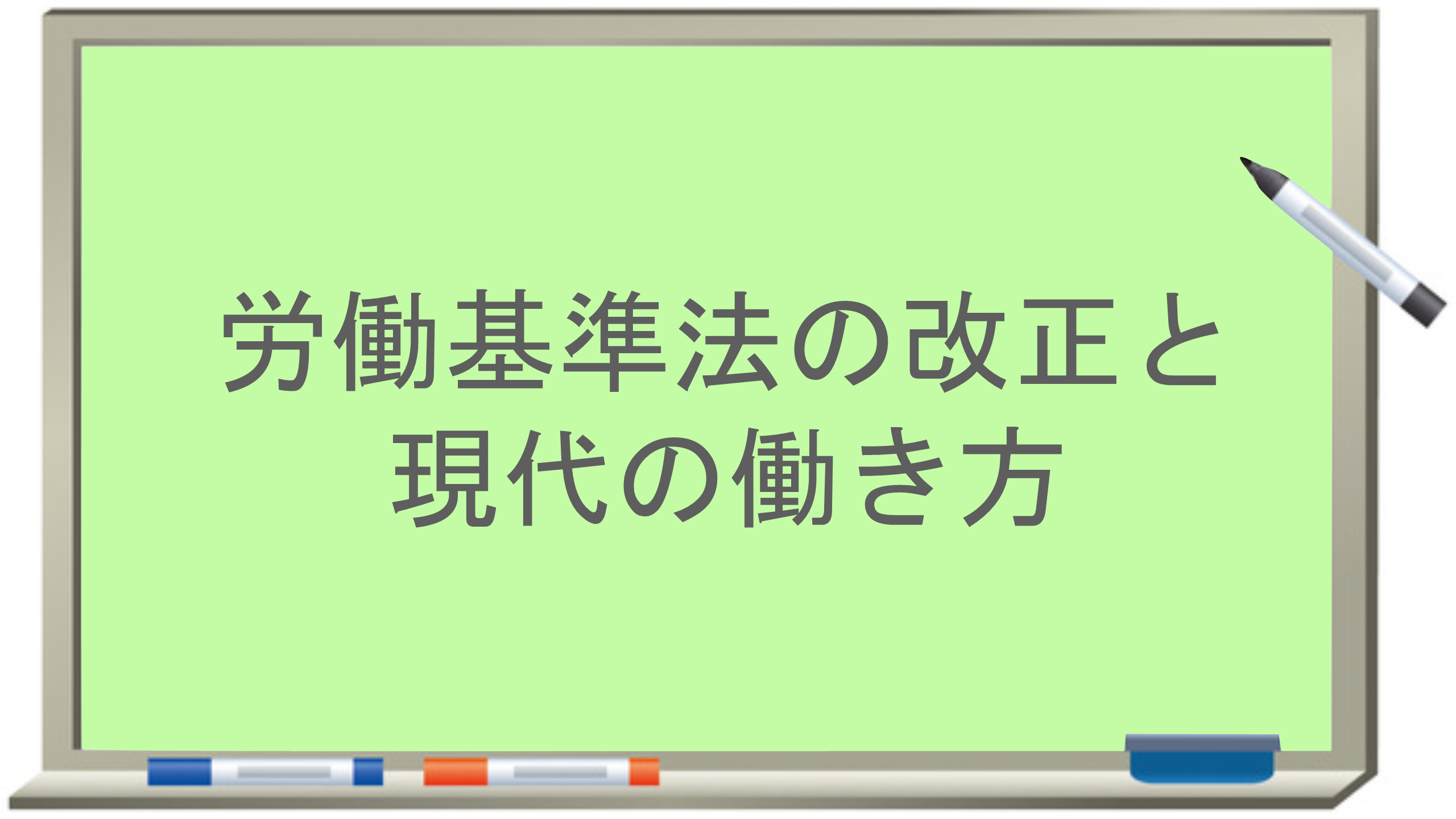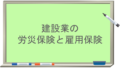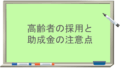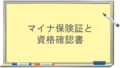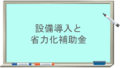東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社労士・コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
最近話題となっている労働基準法の改正の流れについて問い合わせを受けることがありましたので、どのような内容が議論に上がっているのかをまとめて見たいと思います。
さて、今回は労働基準法の改正が議論されている理由を以下の3点にまとめました。
- 労基法の歴史と背景
- 改正が議論されている内容
- 対策が必要になる点
労基法の歴史と背景
工場法が前身
労働基準法は、労働者を雇用しているすべての会社で知っておく必要がある内容であるとともに、労働者としても知っておいて損はない法律の内容でもあります。
社労士を目指す人が最初に学ぶ科目でもありますし、勉強時間と結果が比例せず苦労している学習者が多い科目とも言えます。
そんな労働基準法が制定されたのは、昭和22年(1947年)に制定されましたが、前身となっているのは大正5年(1916年)に制定された工場法です。
工場で働く労働者が多かったという当時の時代背景を感じる名前ですね。
| 主なポイント | |
| 昭和22年(制定時) | 現在の働き方のベースが完成 1日8時間、週48時間 125%の割増賃金 労働者災害補償 など |
| 昭和62年改正 | 週40時間に段階的に短縮 フレックスタイム制や裁量労働制の整備 |
| 平成5年改正 | 週40時間に短縮 割増賃金率の引き上げ |
| 平成10年改正 | 時間外労働の限度を定める 企画業務型裁量労働制の導入 |
| 平成15年改正 | 専門業務型裁量労働制に健康確保の措置を追加 |
| 平成20年改正 | 60時間を超える時間外労働の割増率を5割に引き上げ 割増賃金の代替休暇を与えれば割増の支払いが不要に |
| 平成30年改正 | 長時間労働の上限規制の導入 フレックスタイム制の見直し 高度プロフェッショナル制度の創設 有給休暇の5日を取得が義務化 |
時代は変わり、工場以外で働くという選択肢が増えたり、技術の進化や新型感染症の影響で働く場所の自由度が高まり、働き方も多様化してきました。
それぞれのタイミングで、社会情勢を踏まえて法改正が行なわれてきました。
改正の議論されている内容
7つのポイントで動いている
過去にも数回の改正が行われて、今の形となっている労働基準法ですが、今回も現代の働き方に合わせて7つのポイントが改正されようとしています。
ただ、まだ確定と言うことではなく、方向性を示しているだけですので注意が必要です。
| 方向性 | 現状と問題点 | 改正案 |
| 連続勤務の上限規制 | 休日は週1日以上か4週4日以上が必要 ┗最長で48連勤が可能となってしまっている | 連続14日以上の勤務の禁止 |
| 法定休日を明確にすることが義務化 | 法定休日の特定は義務ではない ┗休日労働の割増賃金が正しく支払われていないケースがある | 法定休日を明確にすることを義務化 |
| 勤務間インターバル制度の義務化 | 勤務間インターバル制度は努力義務 ┗制度が普及しておらず、労働者の健康が害されている可能性がある | 勤務間インターバルを11時間以上とすることを義務化 |
| 有給休暇を取得時の賃金計算ルールの明確化 | 平均賃金方式、通常賃金方式、標準報酬月額方式を選択できる ┗働き方によっては金額が少なくなることがあり、労働者に不利益となっている | 通常賃金方式で計算とする |
| つながらない権利のガイドラインの策定 | つながらない権利は明確化されていない ┗勤務時間外にも業務連絡が入ることで、休息の確保がされていないことがある | つながらない権利の社内ルールの策定を推奨 |
| 副業・兼業者の割増賃金の計算ルールの見直し | 副業先との勤務時間を通算して、後に契約した方が割増賃金を支払う ┗企業の負担が大きく、副業を認める障害となっている | 割増賃金の算定では労働時間を通算する必要はない |
| 法定労働時間週44時間の特例措置の廃止 | 要件を満たす事業場では週44時間の特例が認められている ┗特例があるものの利用されている事業場が少ない | 法定労働時間週44時間の特例措置を廃止 |
対策が必要になる点
労務管理体制の見直しが必要
これらの法改正が行なわれた場合に、企業としては何をする必要があるのでしょうか。
ひと言で表すのであれば、「労務管理体制の見直し」となります。
就業規則を作成している会社であれば、法改正に合わせて就業規則を改定する必要が出てきます。雇用契約書にも記載されている可能性がありますので、合わせて修正しておいた方がよいでしょう。
勤怠管理システムや給与計算システムは、ご使用のシステム会社が直してくれる範囲で対応ができるかと思いますが、会社にあわせて作成したシステムであれば改修をすることも視野に入れておく必要があります。
人事などを担当している部署があれば、担当者には変更したあとの内容を理解してもらわなければなりませんし、つながらない権利については、社内ルールを決めるだけではなく従業員にも周知をしっかりとしておきましょう。
終わりに一言
法改正があると、社内での対応が求められますが、本業とは違う内容を細かく見ていくことは難しいところでもあります。
外部の専門家を頼ることはコストの増加というデメリットもありますが、本業に集中できるというメリットもあります。できる範囲を社内で行い、難しい部分は外部を頼るという手段もご検討ください。ご不安なこと、ご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。