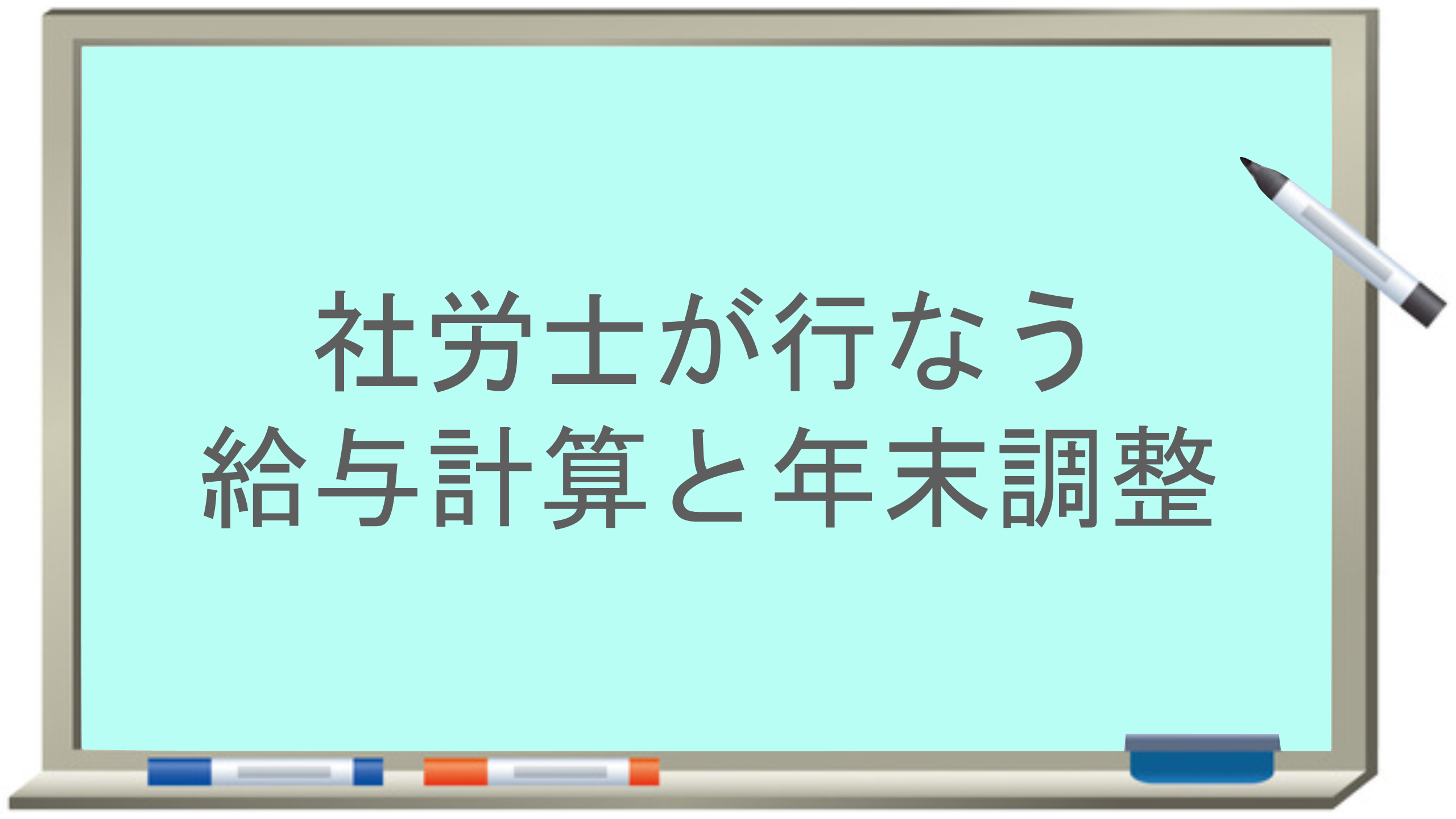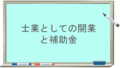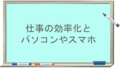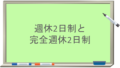東海地方の田舎町で【コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
12月の給与計算が終わってから、年末調整の時期に入りました。
昨年から給与計算を委託いただける会社が増えてきまして、年末調整のデータを反映させたりする必要がありました。
ようやく落ち着きましたので、調べた内容を記事にしたいと思います。
さて、今回は給与計算をしている会社の年末調整について以下の3点にまとめました。
- 年末調整とは
- 年末調整は誰が行なうか
- 年末調整の費用は
年末調整とは
所得税の過不足の調整を行う
従業員を雇っていると毎月給与の計算を行います。
残業代や歩合給など、会社ごとでルールが異なるものを正確に計算していかなければなりません。
給与計算をした情報をもとに会社で給与の支払いを行います。
その際に、いくつか控除するものがあります。給与の情報を見ると、社会保険料や源泉所得税、住民税などが控除されているかと思います。
ここでは、給与から控除するものの金額や役割などを簡単にまとめておきます。
| 健康保険料・厚生年金保険料 | 社会保険の等級表に照らし合わせて、決められた金額を控除します。 保険料率は都道府県ごとに決められており、毎年4月に改正されることがあります。 40歳以上なると介護保険料を納める必要がありますので、料率が若干変わりますが、抜けている会社を見かけることがありますので注意が必要です。 なお、納めるときは同額を事業主が負担して納めることになります。 |
| 雇用保険料 | 毎月の総支給額に、業種ごとに決められた保険料率をかけて計算します。 業種ごとの保険料率は下記の通りとなります。 一般の事業:6/1,000 農林水産・清酒製造の事業:7/1,000 建設の事業:7/1,000 納めるときは別の保険料率が加わりますので、単純に倍ではなく倍以上を負担することになります。 労働保険の中には労災保険もありますが、労災保険料は全額を事業主が負担することになりますので労働者の負担はありません。 |
| 源泉所得税 | 総支給から社会保険料の控除をした後の課税所得額を、源泉所得税額表に照らし合わせて決められた金額を控除します。 数千円単位で区分されており、扶養家族の数によって納税額が変わりますので注意が必要です。 |
| 住民税 | 納税額が市町村から通知されますので、事業主はその金額を給与から控除して納めます。 前年の所得に応じて金額が決まりますので、社会人1年目は控除されないことがほとんどです。 2年目になると1年目の所得に応じて控除されるため、月給が増えても手取り額は減少してしまうということが起こり得ます。 |
源泉所得税は、今月の収入が12カ月間続いたら年収はいくらになるかを計算して所得税額が決まるようになっています。
ただ、毎月の給与に変動があると、引きすぎていたり、逆に引き足りなかったりということも起こってしまいます。
年末調整とは、1年分の給与が決まった段階で、最終的な年収に応じた所得税に過不足がある場合に調整する作業になります。
年末調整は誰が行なうか
税理士さんにお任せする
年末調整は税務関連の業務になりますので、税理士法第2条で定められている独占業務になると思われます。
少し話はそれるかもしれませんが、ファイナンシャルプランニング技能士(FP)の試験の話をします。
学習をすると過去問でよく出てくるのですが、他の士業の独占業務の相談があった場合に答えてもよいかという問題です。相談自体は制限していない士業もありますが、税理士法第2条第1項第3号には相談業務も独占業務であると明記されています。
書類作成や代理についてももちろん明記されていますので、今回のような所得税についての業務を行うことは税理士さんでない場合は避けた方が良いかと思います。
過去には全国社会保険労務士連合会と日本税理士会連合会との間で協議された結果の文章も公開されていますので、年末調整の計算事務は行わない方がよいと判断しました。
毎月の給与計算までは制限されていないようですので、そこは一安心な点でした。
年末調整の費用は
規模により異なる
年末調整は名前の通り、年に1度だけ年末に業務が発生します。
普段とは違う作業が追加で発生しますし期限があることもあり、月々の顧問料とは別で報酬が必要になるケースが多いです。これは決算も同様になっていることが多いようです。
社労士で言うところの、算定基礎届や年度更新の手続きのようなものでしょうか。
共通しているのは年に1度の業務という点ですので、社内で覚えさせて何かを見ながらやるよりは外部の専門家に外注してしまった方がよいという判断になるでしょう。
では、外注するときの費用がいくらになるのかという点ですが、これは正直規模によって異なるということになってしまいます。
従業員の数が多ければ計算する数も多くなりますので、作業工数も多くなります。
参考までにインターネット上で検索してみましたが、1か月分としているところから2~10万円としているところまで様々でした。
税理士や社労士の顧問料は人数規模により変わることが多いですので、定額で○○円となっているところであればもしかしたら割安になるのかもしれません。
終わりに一言
源泉所得税の計算自体はシンプルですが、万が一間違ってしまったときのリスクは抱えてしまいます。
事業を行っていく中で、頻繁に起きないことに関しては内製化するよりも外注してしまった方がよいということも往々にしてあります。
弊所では年末調整は行っていませんので、税理士さんがいらっしゃらない場合は別で探す必要がありますが、懇意にしている税理士事務所をご紹介することもできます。
社労士業務であれば、取得や喪失などの手続きも頻繁に起きない分野になる規模の会社も多いと思います。担当を置くのではなく、これを機に外注を検討されてみてもよいかもしれません。弊所では労務相談から手続き代理、給与計算や助成金対応まで受け付けております。気になる方はお気軽にお問い合わせください。