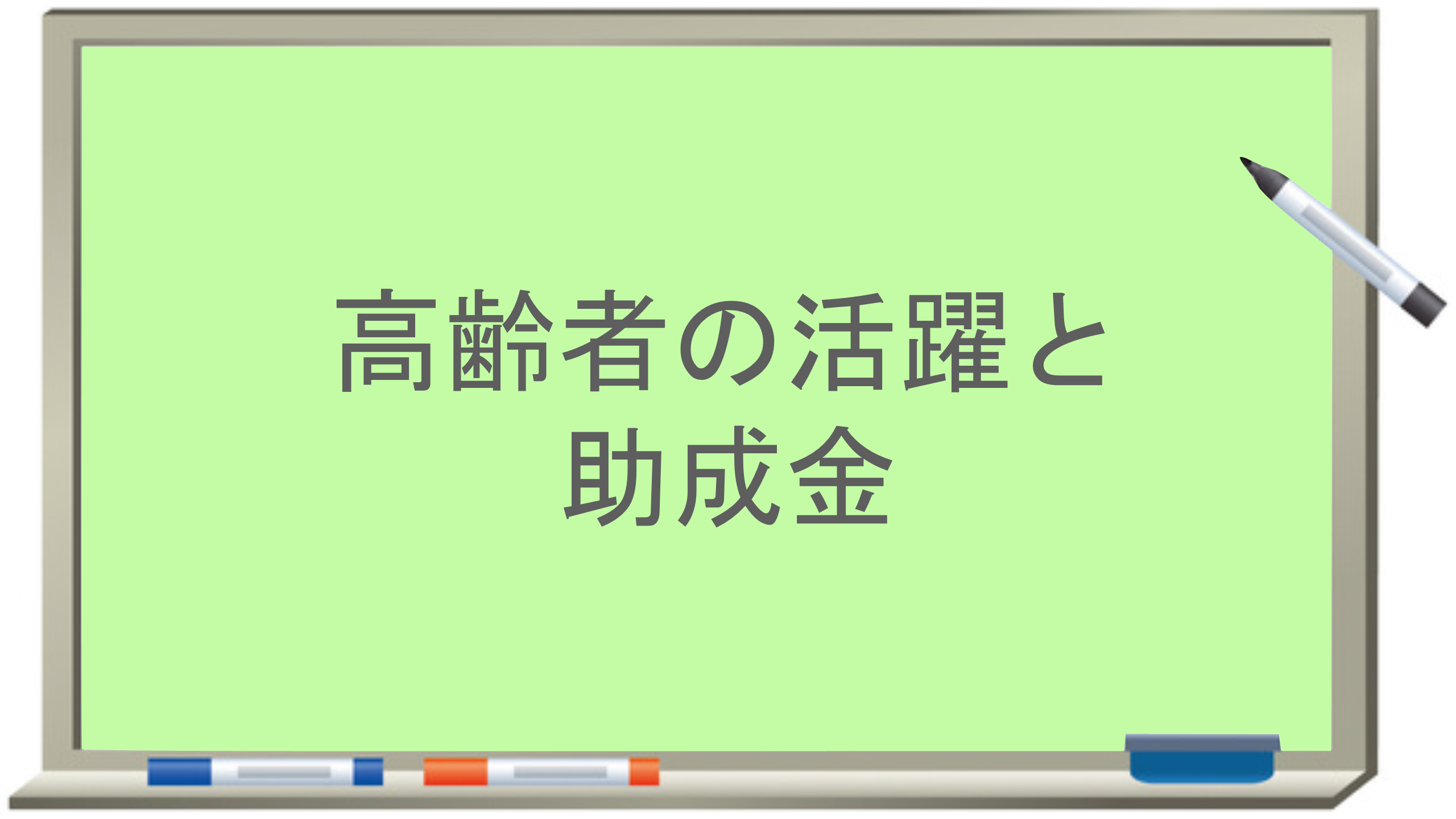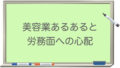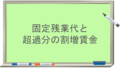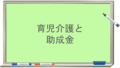東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社労士・コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
最近の60代、70代は元気な方が多く、定年の引上げや平均寿命の伸びもあり、長く働ける社会になったのではと感じています。
私の周りでも現役で仕事を持っている方が多くいらっしゃいます。
ちなみに、私が勤めていた前職は転職で入社をしていますが、実は学生時代の企業調査で調べたことがあります。そのときは35歳定年という情報を目にしました。
当時は今ほどはインターネットが普及していませんでしたので、35歳定年ということの裏どりもできないまま、そんなものかと受け止めていた覚えがあります。
実際に働いてみて、35歳定年はある意味で正しくて、ある意味で間違っていたなという印象です。
さて、今回は高齢者が活躍できる社会と活用できる助成金について以下の3点にまとめました。
- 日本の定年年齢の推移
- 労働力不足の解消のために
- 助成金の概要
日本の定年年齢の推移
初期のころは55歳だった
定年年齢が伸びてきていることの背景には、日本の平均寿命の延びが影響しています。
厚生労働省の情報によりますと、令和2年の平均寿命は男性で81.27歳、女性で87.45歳となっています
少し遡り昭和40年代からの平均寿命の推移をまとめてみました。
| 年代 | 男性 | 女性 |
| 昭和40年 | 67.74 | 72.92 |
| 昭和50年 | 71.79 | 77.01 |
| 昭和60年 | 74.95 | 80.75 |
| 平成2年 | 76.04 | 73.22 |
| 平成7年 | 76.70 | 83.22 |
| 平成12年 | 77.71 | 84.62 |
ちなみにですが、昭和40年生まれの方は令和7年で60歳(還暦)を迎えます。
つまり、60年前から今までで平均寿命は15歳ほど伸びているということになります。
では、定年の年齢は推移してきたのでしょうか。
私が生まれたころの定年と言えば、60歳と言われていたように記憶しています。
しかし、まだ60歳定年が義務化されているわけではなく、努力義務でした。
出生率の低下や団塊の世代の定年が現実化してきた頃に60歳定年が義務化され、気が付けば65歳定年が義務化されるまでになりました。
労働力不足の解消のために
ベテランのスキルを活かす
定年年齢の上昇に伴い、企業の平均年齢も上がっていく傾向になります。
しかし、悪いことばかりではありません。
長く同じ会社に勤めているということは、それだけいろいろな経験をしているということも言えます。
若手では手に負えない事態が起きてもどっしりと対応してもらえるという安心感があります。
もちろん、長くいるだけが立派ということではなく、若手の経営者が新しい技術やマーケティングを活用してビジネスを成長させている企業があるのも事実です。
しかし、日本の多くの中小企業ではまだまだシステム化や機械化が追い付いていない状況もあります。
ベテラン職人の持つ技術は一朝一夕で身につくものではありませんので、会社にとっては財産となることも多くあります。
職人の持つ技術以外でも、営業や人材育成などのノウハウも、言語化できていない部分がまだまだあるのではと見ています。
もちろん、労働力という観点でも、働きたいと考えている方に、働き続けてもらうということは双方にとってメリットが多くあります。
65歳超雇用推進助成金
この助成金は私が最近よくお話をする機会が多い助成金の一つとなります。
概要
高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会の実現を行う事業主を支援する目的で実施されている助成金となります。
1.65歳超継続雇用推進コース
65歳以上への定年引上げ、定年の廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入などを実施した事業主に対して助成する
2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等の措置を実施した事業主に対して助成する
3・高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成する
活用事例
活用が比較的しやすい前述の1のコースについて簡単にまとめた上で、活用事例をご紹介します。
要件は、A:65歳以上への定年年齢の引き上げ、B:定年の廃止、C:希望者全員を66歳以上の継続雇用制度の導入、D:他社による継続雇用制度の導入の4つのいずれかを実施することです。
| 60歳以上の人数 | 定年を引上げ | 定年の廃止 | 継続雇用の導入 |
| 1~3人 | 15~30万円 | 40万円 | 15~30万円 |
| 4~6人 | 20~50万円 | 80万円 | 25~50万円 |
| 7~9人 | 25~85万円 | 120万円 | 40~80万円 |
| 10人以上 | 30~105万円 | 160万円 | 60~100万円 |
前提として、60歳以上の方が1人以上いる事業所でしか活用はできませんが、いらっしゃるのであれば活用しない手はありません。
細かくは引き上げる年齢幅に応じて変動がありますので、詳しくは参照のリンクをご覧いただくか、弊所までお問い合わせていただければご説明させていただきます。
定年の年齢の引き上げを実施することがシンプルですが、パフォーマンスが衰えてきたときに同じように雇用し続けることは現実的ではありません。
その場合は、継続雇用制度を導入し、嘱託社員として継続して契約をしていくという手を使うこともできます。
希望者は全員雇用することになりますが、雇用条件は個別で取り交わしますので前年の働きに応じて雇用条件を提示することもできます。
上手く活用することができれば労働力の確保だけでなく、ノウハウを伝承し若手の育成、助成金獲得までできてしまいます。
終わりに一言
最近よく聞かれる助成金でしたので、事務局に問い合わせた内容も含めてご紹介させていただきました。
最近の60歳は元気な方が多い印象がありますので、過去の経験やノウハウを自社業の発展に活かしてもらうために採用に力を入れてみることもご検討ください。
助成金の申請や就業規則の修正でお困りごとがありましたらご相談にのっていますので、お気軽にお問い合わせください。