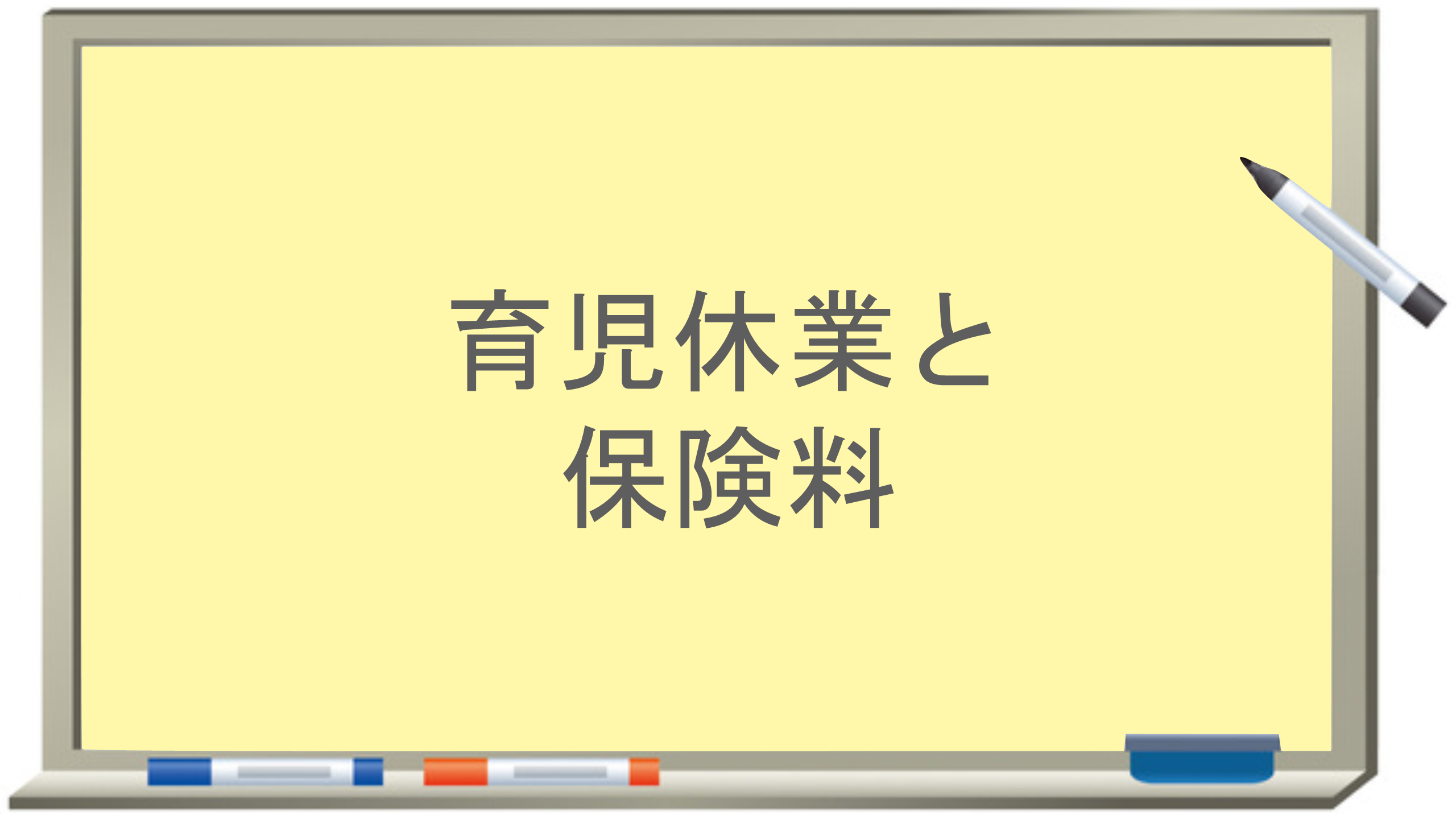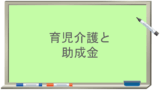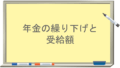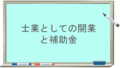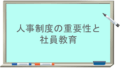東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社労士・コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
社会人生活の中で結婚や子育てなどのイベントが起こることがあります。
おめでたいことではありますが、労働者使用者ともに考えることが増えるのも事実です。
最後に助成金の話も書いてありますので最後までお読みいただけると嬉しいです。
さて、今回は育児休業の際の保険料について以下の3点にまとめました。
- 保険料免除の対象
- 社会保険料について
- 労働保険料について
保険料は納めるのか
免除の対象となる
まず最初に、出産を控えている従業員が休業に入る場合、大きく分けて産前休業、産後休業、育児休業の3つの段階があります。
そして、従業員本人ではなく配偶者の出産に伴っての休業ということもあります。
また、狭義の社会保険として労働保険(労災保険、雇用保険)があります。
上記で記載している休業はほとんど保険料免除の対象となっています。
ここで言う保険料免除とは、従業員が負担する分だけでなく、会社が負担する分も免除されることとなっています。
なお、労働保険料も実質的には免除されることとなっていますが、免除という考え方とは少し違います。後半でご説明します。
対象にならないケース
従業員が出産をする場合で免除とならないことはあまりありませんが、気を付けなければならないのが配偶者の出産のために男性が休業する場合です。
育児休業の期間中に保険料を免除するためには以下のような要件があります。
①月末が育児休業の期間中であること
②同一月内に開始と終了がある育児休業は14日以上であること
③賞与の場合は、1ヶ月を超える育児休業を取得していること
男性の育児休業取得を推進している背景もあり、出産に合わせて1週間程度休むこともあるかもしれませんが、その場合は月末をまたいでいないと免除の対象となりませんのでご注意ください。
保険料について
社会保険料は免除される
では、いつから健康保険や厚生年金の保険料が免除となるのでしょうか。
免除の期間としては、法律上は次のように書かれています。
「産休を開始した日の属する月からその産休を終了する日の翌日が属する月の前月まで」(健康保険法第159条の3、厚生年金保険法第81条の2の2)
「育休を開始した日の属する月からその産休を終了する日の翌日が属する月の前月まで」(健康保険法第159条、厚生年金保険法第81条の2)
とても分かりづらい書かれ方をしていますので出産日を基準に具体的な日で見ていきましょう。
・出産予定日:5月27日
・産前休業:4月16日~5月27日
・産後休業:5月28日~7月22日
・育児休業:7月23日~5月26日
・社会保険料の免除期間:4月~翌年4月分
つまり、産前産後や育児のため休んでいる期間の保険料は免除されるということになります。
労働保険料も実質免除される
労働保険料は免除と言う考え方ではないと書きましたが、近いものであることに違いはありません。
そろそろ時期になっていますが、労働保険料の納付は主に年に1回、7月10日までに申告することとなっています。これは、年度更新という作業になります。
労働保険料の金額は、今くらいの時期に昨年度の賃金支払総額を労基署に提出し、計算します。
産前産後休業や育児休業を取得している期間は、出産手当金や育児休業給付金といった公的の制度があるため、給料は支払われないことがほとんどです。
そのため、賃金支払総額が増えることがありませんので労働保険料を支払うこともないということになります。
人手不足の支援について
公的の制度
出産や育児のために休業するときの支援はいくつかあります。
会社としても慣れている方に戻ってきてもらう方がメリットが多くありますので、上手に活用していきましょう。
・出産手当金:出産の日以前42日から出産の日後56日までの働いていない期間に賃金の2/3を支給
・出産一時金:出産費用の経済的負担を軽減するために支給
・育児休業給付金:1歳に満たない子を養育するための休業をしている期間に賃金の50%から67%を支給
保険料免除と合わせると、手取り額は大きく下がることがないような制度となっています。
細かくは知らなくても問題ありませんが、上記の上2つは健康保険から、下1つは雇用保険から出ていて届出先が違うので注意が必要です。
使える助成金
少し話はそれますが、育児休業を取得した従業員がいると受給できる助成金があります。
従業員が休業に入ると、他の方に負担が偏ってしまったり、臨時で雇う必要が出てくる事業所もあるかもしれません。
そういったときにも受給できる助成金もあります。
最近は、育児休業を取得しながら長く働ける職場を選んでいるという声も聞きますので、採用の強化のためにも制度を設けておくとアピールの材料にもなるかもしれません。
助成金については下記のブログでまとめていますので、ご興味がある方は是非ご一読いただけると嬉しいです。
終わりに一言
育休による負担をなるべく軽減できる制度も活用しつつ、人材確保や社内の強化を図れるとよい会社となっていけるのではと考えています。
助成金だけでなく、制度設計やお手続きも承っております。気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください。