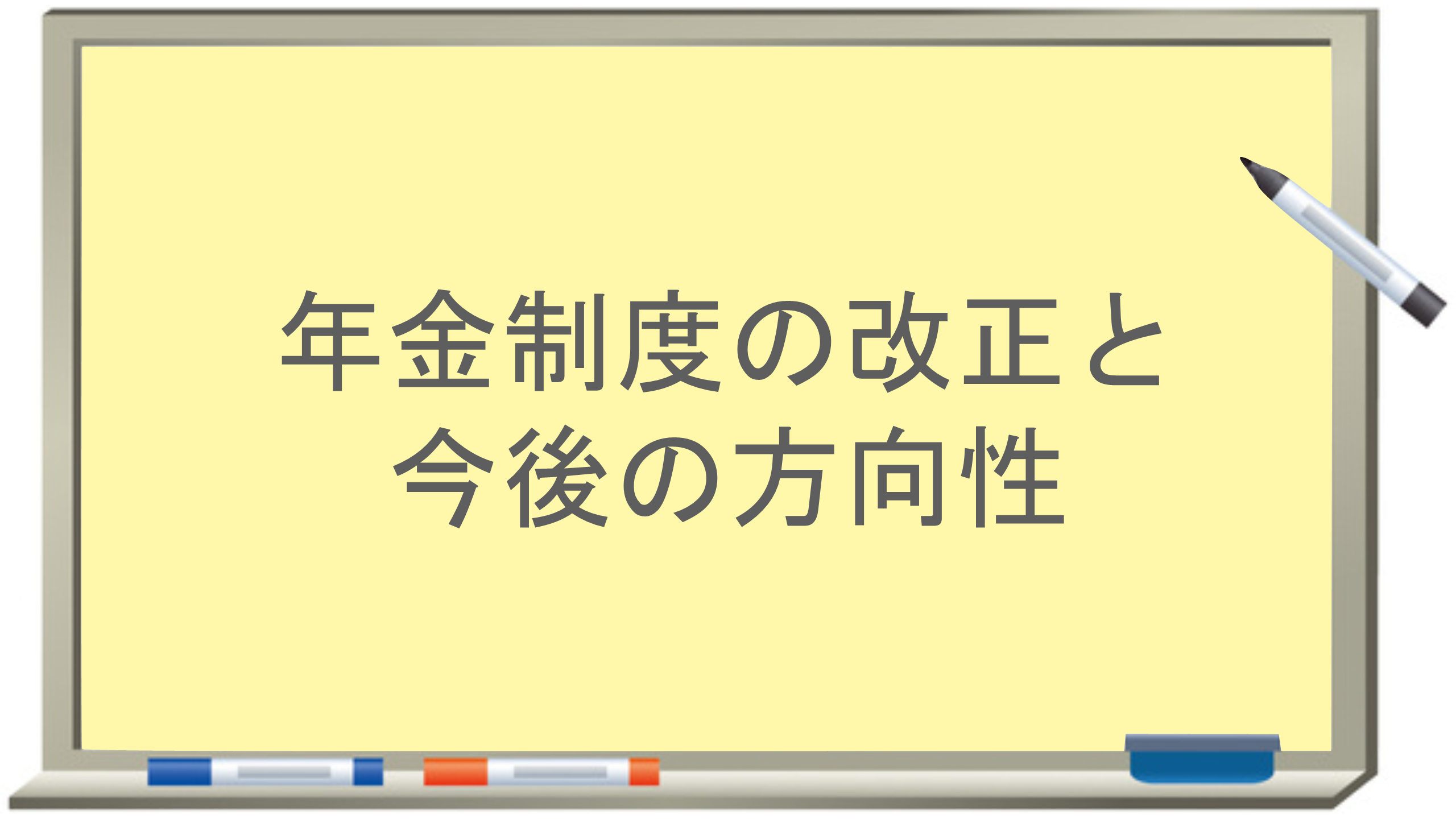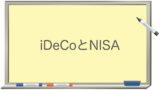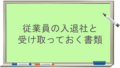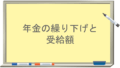東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社労士・コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
先月末の国会にて、年金制度の改正が決まりました。すぐに対応が必要となる事業所から少し先まで特に動きがない事業所までさまざまではありますが、動きは追っておきたいところです。
さて、今回は年金制度の改正について以下の3点にまとめました。
- 加入対象の改正
- 加入中の改正
- 受給の改正
今回の記事を書く上で参考にした資料は厚生労働省のこちらのページになります。
加入対象の改正
加入対処の拡大
年収の壁が3年以内になくなるということが決まりました。
今までの加入対象者からどのように変わったのかというところを比較してみたいと思います。
| 今まで | これから | |
| 月額給与 | 88,000円以上 | 撤廃 |
| 勤務時間 | 20時間以上 | 20時間以上 |
| 学生 | 対象外 | 対象外 |
| 事業規模 | 51人以上 | 順次撤廃※ |
最初に書かれている月額給与が撤廃されます。
これにより、一時期話題になった「年収106万円の壁」というものがなくなることになります。
週の勤務時間が20時間以上や学生は対象外という点は変わらずとなります。
そして、「※」としている箇所が今後10年をかけて徐々に変更していく部分になります。
参考までに、過去からの人数の動きを表にまとめてみました。
私が社会保険を学習していたときは501人以上と覚えていましたが、気づけば51人以上になっていました。
それがこれから段階的に小規模も対象になり、約10年後にはすべての事業所が対象になるようになります。
| 2016年10月~ | 2022年10月~ | 2024年10月~ | 2027年10月~ | 2029年10月~ | 2032年10月~ | 2035年10月~ |
| 501人以上 | 101人以上 | 51人以上 | 36人以上 | 21人以上 | 11人以上 | 10人以下 |
私的年金制度の見直し
こちらは3年以内に実施ということまで公表されており、具体的な時期は未定となります。
私的年金制度というと耳なじみはないかもしれませんが、iDeco(イデコ)と言われると聞いたことがある方が増えるかもしれません。
加入対象年齢は2020年までは60歳までとなっていました。それが2020年の法改正で65歳まで加入できることになっており、それが現在まで続いていましたが、今回の法改正で70歳までに拡大されます。
ただし、年齢以外の加入要件である、「老齢基礎年金」やiDecoの「老齢給付」を受給していない人というものはそのままとなっています。
年齢以外にも、掛金の上限も引上げられる予定ですので、老後の資産形成を考える手段が増えるのはいいことだと考えています。
イデコについては過去の記事でもまとめていますので、ご興味がある方はご一読いただければと思います。
加入中の改正
在職老齢年金制度の見直し
在職老齢年金も金額が良く変わるところです。
次の改正では2026年4月から変更となります。
まず、制度としては、年金を受給しながら働くときに、給与と年金の合計額が一定の金額以上になると、年金額が減らされるというものです。
せっかく働いても、年金が減ってしまうので働くのを控えてしまうということも起こっていました。
以前は年齢別で28万円以上が対象となっていましたが、現在では50万円以上となっており、それが62万円に引き上げられます。
これにより、年金を受給しながら給与所得があったときにも年金が減らされる可能性が減ります。
働くのを控えていた方ももっと働くことができるようになるのではないでしょうか。
標準報酬月額の引上げ
標準報酬月額は、社会保険料や厚生年金の支払いのときに影響する印象が強いですが、年金を受け取るときにも影響します。
今回の改正で、2027年9月から段階的に引き上げられることが決まりました。
今の標準報酬月額の等級表では、健康保険は50等級(139万円)と厚生年金(65万円)と一番上の等級が決められています。
今回の改正で、厚生年金の一番上の等級が75万円まで上がることがきまりました。
全体的な賃上げの動きがある中で、多くの月収をもらっている人にも保険料を負担してもらおうという趣旨が見えます。
ネガティブな印象が強いですが、標準報酬月額が上がることによって年金額もあがりますので、将来もらえる額としては増えるので、悪い部分ばかりでもありません。
受給の改正
遺族年金の見直し
遺族年金はややこしい制度でしたので、覚えるのに苦労した記憶があります。
今まであった男女差がなくなり、受給できる対象の範囲が広がることはよい改正ではないかと思います。
遺族厚生年金の主な変更点を以下の表にまとめました。
| 今まで |
| 女性 30歳未満で死別→5年間の有期給付 30歳以上で死別→無期給付 |
| 男性 55歳未満で死別→給付なし 55歳以上で死別→60歳から無期給付 |
| これから |
| 男女共通 60歳未満で死別→原則5年間の有期給付 (一部)5年目以降も給付を継続 60歳以上で死別→無期給付 |
そして、遺族基礎年金の変更点は次の通りとなります。
今までは、父や母と同居している子どもは受給できないという制限がありましたが、これがなくなります。
| 今まで | これから |
| 元夫の死亡後に遺族基礎年金を受給していた妻が再婚した ┗妻も子どもも遺族基礎年金を受け取れない | 子どもは妻(子どもの母)と生計が同じでも遺族基礎年金を受け取れるようになる |
| 夫の死亡後でも妻は収入要件を超えていて遺族基礎年金を受け取れない ┗子どもは妻(母親)と生計が同じだと遺族基礎年金を受け取れない | 子どもは妻(子どもの母)と生計が同じでも遺族基礎年金を受け取れるようになる |
| 離婚後、子どもを養育していた元夫が死亡した ┗元妻は元夫の死亡より前に離婚していたため遺族基礎年金を受け取れない | 子どもは元妻(子どもの母)に引き取られて生計が同じになっても遺族基礎年金を受け取れるようになる |
| 子どもは祖父母などの直系血族の養子になって生計が同じになっても遺族基礎年金を受け取れるようになる |
なんで男女差があるのかということは受験生時代も疑問でしたが、とある先生が女性は再就職が難しいという背景にあげて教えてくださっていて、とても分かりやすかったのを覚えています。
終わりに一言
年金は金額が定期的に変わるため、法改正は多い印象でしたが、今回のような改正は久しぶりな気がします。
遺族年金の対象となる方は少ないかもしれませんが、それ以外にも多くの法改正がありましたので、全体的には影響がある方が多いでしょう。
社内で対応が難しいときや、確認が必要となったときにはお気軽にお問い合わせください。