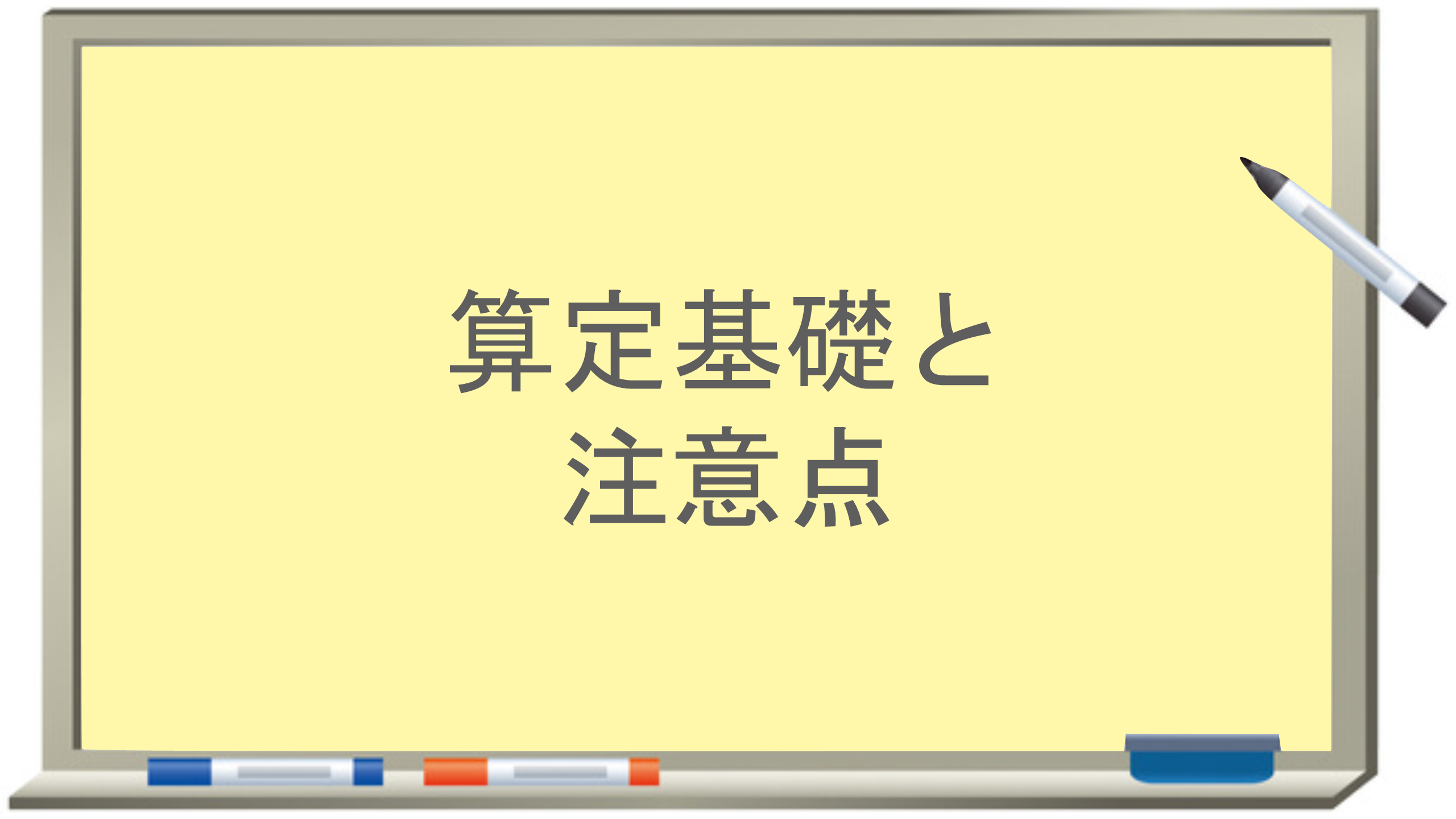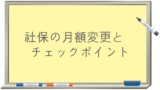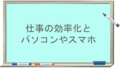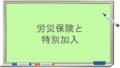東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社労士・コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
7月10日までに出さなければならない手続きの一つが算定基礎届です。
年度更新の時期と重なっていますので、届け出るのを忘れないようにしなければなりません。
実はもう過ぎているのですが、出さなくてよいものではありません。
まだの場合は早めに出しておきましょう。
さて、今回は算定基礎届と手続きをする上での注意点を以下の3点にまとめました。
- 算定基礎とは
- パターンごとの注意点
- よくある質問
算定基礎とは
9月からの等級を決める
算定基礎届というものが6月くらいになると会社に届います。
これは、毎年4~6月に支払った給与をもとに9月から翌年8月までの標準報酬月額を決めるために必要な書類になります。この手続きのことを定時決定と呼んでいます。
| 提出期限 | 毎年7月1日から7月10日まで |
| 提出先 | 年金機構の事務センターか所轄の年金事務所 |
| 提出方法 | 届いた封筒に同封されている返信用封筒で郵送 窓口に持参 電子申請 |
対象となる人とならない人
対象となる人は、7月1日時点で厚生年金や健康保険の被保険者となっているすべて労働者です。
正社員だけでなくパートも対象となります。
他にも、育児休業や介護休業で休業中の労働者や、私傷病で休職中の方も対象となります。
対象とならない人は、次のいずれかに当てはまる人です。
①6月1日以降に資格取得した人
②7月改定の月額変更届を出す人
③8月か9月に随時改定を予定している人
どれかに当てはまっている労働者は申請するときに名前を書かなくてよいですし、日本年金機構から届く書類に名前が書かれていたら「月額変更予定」に丸をつけて届け出れば問題ありません。
対象となる給与
対象となる給与は、労働者が労働の対価として受け取るすべてのものとなります。ここでは支給されるときの名称は問われていません。
また、制服や社宅といった現物で支給されるものも含みます。
賞与については、年に4回以上支給されるものが対象となります。
| 通貨で支給されるもの | 現物で支給されるもの | |
| 報酬となるもの | 基本給、職務給、職能給、家族手当、通勤手当、別居手当、時間外手当、年4回以上の賞与、等 | 通勤定期券、食事、社宅、被服、自社製品、等 |
| 報酬とならないもの | 見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費、慶弔見舞金、傷病手当金、等 | 制服、、作業着、食事、等 |
支払い基礎日数の計算
計算をするにあたって、労働者をいくつかの区分に分けておく必要があります。
これは、どこの対象になっているかによって、必要となる日数が変わってくるためです。
・一般的な労働者
・短時間就労者(パートなどの名称を問わず、正社員よりも短い時間で勤務する人)
・短時間労働者(正社員の3/4基準を満たしていなく、必要な要件を満たしている人)
一般的な労働者の場合は、17日以上の月を対象として計算をしますので、17日未満の月があったとしたらその月の給与は除いて計算します。
| 基礎日数 | 決定方法 |
|---|---|
| 3か月とも17日以上 | 3か月の平均額 |
| 17日未満の月がある | 17日以上の月の平均額 |
| 3か月とも17日未満 | 前の標準報酬月額 |
短時間就労者の場合は、基本的には正社員と同じように17日以上の月を対象として計算しますが、17日未満の月であっても15日以上である月であれば対象となります。
| 基礎日数 | 決定方法 |
|---|---|
| 3か月とも17日以上 | 3か月の平均額 |
| 17日未満の月がある | 17日以上の月の平均額 |
| 3か月とも15日以上17日未満 | 3か月の平均額 |
| 15日以上17日未満の月と15日未満の月がある | 15日以上17日未満の月の平均 |
| 3か月とも15日未満 | 前の標準報酬月額 |
短時間労働者の場合は、11日以上の月を対象として計算をしますので、11日未満の月があったとしたらその月の給与は除いて計算します。
| 基礎日数 | 決定方法 |
|---|---|
| 3か月とも11日以上 | 3か月の平均額 |
| 11日未満の月がある | 11日以上の月の平均額 |
| 3か月とも11日未満 | 前の標準報酬月額 |
パターンごとの注意点
どの月を対象とするかが変わってくる
すべての労働者がフルタイムで働いているのであればとても簡単なのですが、イレギュラーなことも起こってきます。
よくあるイレギュラーなケースとしては、4月1日入社で期間が3か月ないケースや、途中で短時間労働者になっているケースです。
賞与が4回以上出ているケースはあまり見かけませんが、四半期ごとのインセンティブなどが支払われていると、4回以上となりますので注意が必要です。
| 月によって被保険者の区分が違う | 区分ごとに対象かを判断 |
| 期間の途中で入社した | 1ヶ月分が支給されている月が対象 |
| 年4回以上賞与が支払われている | 賞与の合計を12で割った金額を各月に加算 |
よくある質問
算定基礎届のQ&A
- Qどの方法で提出したらよいのでしょう?
- A
電子申請であれば処理が早く済みますのでお勧めです。パソコンが苦手と言う方は届いている紙に記入して郵送しても構いません。
- Q届いた用紙に名前がない労働者がいるのですが、どうしたらよいですか?
- A
空いている行に追記して提出します。
- Q算定基礎のあとで月額変更がありましたが、どうなりますか?
- A
7月から9月を改定とする月額変更届を出すと、月額変更が優先されます。
- Q1時間だけしか働いていない日がありますが、対象になるのでしょうか?
- A
1時間だけの勤務でも1日分として対象となります。
- Q半年分の定期代を支給したときはどうしたらよいのでしょう?
- A
半年分で支給した金額を対象の6か月で割って、1か月分の報酬に加えます。
- Q手当の支払い月が変更になったときはどうしたよいのでしょうか?
- A
変更月には手当が支給されませんので、対象から除きます。
- Q社会保険適用促進手当を支給しているときは除いていいのでしょうか?
- A
社会保険適用促進手当の特例を使用する場合は、除いて計算しても構いません。
- Q20日締め末日払いの場合、4月分の給与が1か月分に足りませんがどうしたらよいでしょうか?
- A
4月は1か月分の給与が支給されていませんので、対象外となります。
- Q例年4月から6月に残業が多く発生しますが、そのまま提出してよいのでしょうか?
- A
年間の平均との差が大きいのであれば、年間平均で計算ができます。備考欄の年間平均に記載の上、必要書類を添付して提出します。
終わりに一言
算定基礎は用紙が届くことや、対象となる月が3か月と少ないこともあり、書類を作成することの手間は年度更新に比べると多くない印象です。
給与計算を自社で行っている場合はデータが手元にあるので集計も簡単にできます。
これは私の主観ですが、社長の本業は会社の成長のための経営について考えることだと考えています。年に1度しかない業務のやり方を頑張って覚えるのではなく、専門家に依頼してみてはいかがでしょうか。お気軽にお問い合わせください。