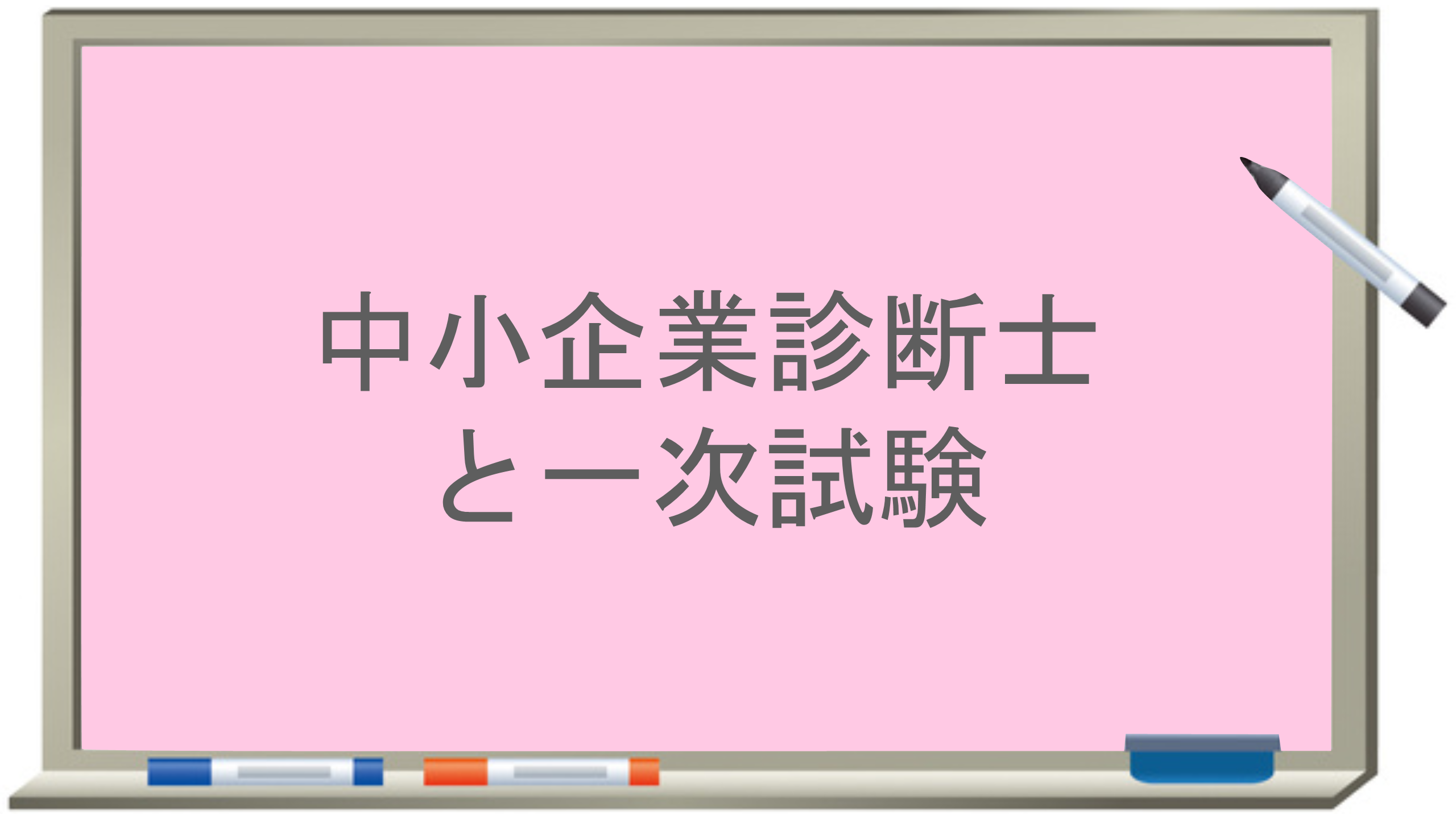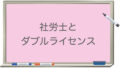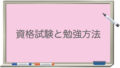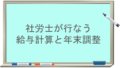東海地方の田舎町で【コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
コンサルタントを名乗るために資格は必要ありませんので、誰でも名乗ることができます。社労士でも「労務コンサル」などと名乗っている人は多くいらっしゃいます。
私もその一人ですが、「集客コンサル」としての活動の方が多いです。ただ、体系的な経営の知識が足りていないことを痛感しており、経営コンサルタントの唯一の国家資格である中小企業診断士を勉強することにしました。
社労士よりも大変だと感じた中小企業診断士の試験について今回から3回に分けてまとめていきたいと思います。
さて、今回は私が勉強した中小企業診断士について以下の3点にまとめました。
- 中小企業診断士の試験とは
- 一次試験の試験内容
- 一次試験の勉強方法
中小企業診断士の試験とは
試験の概要
中小企業診断士という資格は国が認める唯一の経営コンサルタントとしての国家資格を持つ人のことを言います。
経営の診断や経営に関する助言をすることができ、企業の戦略策定やその実行のためのアドバイスも行います。
その他にも、中小企業と行政や金融機関をつなぐパイプ役や、助成金申請の際のアドバイスなども行なっています。
そんな中小企業診断士になるためには、一次試験、二次試験と口述試験の3つを通過した後に、実務従事や実務補修を経て登録が可能になります。
一次試験では、7科目を受験することになります。
| 日程 | 試験科目 | 試験時間 |
| 1日目午前 | 経済学・経済政策 | 60分 |
| 1日目午前 | 財務・会計 | 60分 |
| 1日目午後 | 企業経営理論 | 90分 |
| 1日目午後 | 運営管理 | 90分 |
| 2日目午前 | 経営法務 | 60分 |
| 2日目午前 | 経営情報システム | 60分 |
| 2日目午後 | 中小企業経営・中小企業政策 | 90分 |
合格基準は次の2つがあります。
①受験した科目の、総得点の60%以上、かつ1科目でも満点の40%未満がないこと
②科目合格基準は満点の60%以上であること
1つ目の基準は、総得点の60%以上ですので全7科目を受験した場合は420点以上で合格となります。
2つ目の科目合格は、もし1年で420点以上とならなかった場合でも、60点以上あった科目は科目合格となり翌年度と翌々年度は受験が免除となるものです。
1つ目のところに受験した科目とあるのは、科目合格や一定以上の要件を満たすことで受験を免除されることがあるためです。
一例ですが、財務・会計の科目は、公認会計士や税理士、弁護士の資格を保有していると免除となります。
ただ、税理士さんであれば財務会計の知識はありますので、あえて受験して得点源とするという選択もあります。
難易度と学習時間
一次試験の合格率は例年30%前後となっています。
直近ですと、最も高い年で2020年の42.5%、低い年で2017年の21.7%となります。
なお、令和6年は27.5%、令和5年は29.6%でした。
この合格者には科目別合格は含まれておらず別で集計されており、科目別合格率は下記の表の通りとなります。
高い科目で40%から低い科目で5%台とムラがあります。このムラは科目ごとだけではなく受験年度によっても異なります。
直近2年の合格率を見てみましょう。
| 令和6年度 | 令和5年度(延期となった沖縄を除く) | |
| 経済学・経済政策 | 14.31% | 13.11% |
| 財務・会計 | 15.10% | 14.28% |
| 企業経営理論 | 39.92% | 19.83% |
| 運営管理 | 26.77% | 8.86% |
| 経営法務 | 13.23% | 25.58% |
| 経営情報システム | 15.59% | 11.40% |
| 中小企業経営・中小企業政策 | 5.58% | 20.63% |
前年が難しくなっていると翌年は易しくなるという話も聞きますが、実際のところは分かりません。
令和6年は、企業経営理論と運営管理が前年比で約20ポイントも低下しているため難しくなったと言えますが、全体の合格率では逆に上がっています。
科目合格の制度があるため一度に7科目すべてを勉強しなくてもよいという選択をできる点では、取り組みやすいかもしれません。
一般的に勉強時間は1,000~1,200時間と言われています。ただ、これは二次試験も合わせた勉強時間とされているため、一次試験に限れば800時間前後が必要だと感じています。
一次試験の試験内容
1日目
| 経済学・経済政策 | 経済指標の見方、国際経済、主要経済理論、市場メカニズム、消費と生産の理論、組織と戦略の経済学など |
| 財務・会計 | 簿記、企業会計、原価計算、経営分析、利益と資金の管理、証券投資、企業価値など |
| 企業経営理論 | 経営戦略論:企業戦略、競争戦略、技術経営、国際経営戦略など 組織論:組織構造、組織文化、人間関係、組織変革、人的資源管理など マーケティング論:マーケティングの基礎概念、消費者行動、ブランディングなど |
| 運営管理 | 生産管理:生産管理概論、生産・作業・設備・物の管理など 店舗管理:店舗・商業集積、商品仕入れ。販売、流通情報システムなど |
2日目
| 経営法務 | 会社法、知的財産権、取引関係・企業活動に関する法律知識など |
| 経営情報システム | 情報通信技術:情報処理、データベース、通信ネットワークなど 経営情報管理:情報システムの開発・マネジメント、意思決定支援など |
| 中小企業経営・中小企業政策 | 中小企業経営、中小企業政策など |
2日間に渡る試験の日程を考慮しますと難易度は高いように感じます。
逆に、各科目ごとで分かれているため科目を絞って直前の詰め込みが有効とも言えます。
科目合格の制度がありますので、二次試験に影響の大きい科目は二次試験を受ける年度に残しておいて、あまり影響のない科目を先に終わらせておくという戦略を取ることもできます。
一次試験の勉強方法
インプット
中小企業診断士の一次試験の対策としては、一部は理論を理解して応用にも対応できる必要はありますが、基本的には丸暗記となると感じます。
特に、2日目の科目となる暗記3兄弟と言われる「経営法務」、「情報システム」、「中小企業経営・政策」は完全に暗記科目となります。
初日の科目もメインは暗記だと思っていますが、「企業経営理論」や「運営管理」などは単純な暗記だけでは合格ラインに届かない可能性もありますので注意が必要です。
ベースとなる理論の暗記はもちろんのこと、なぜそのような理論となるのか、応用をすると何が言えるのかというところまで問われている年度もあります。
社労士のときにミスをしましたが、テキストの劣化版を手作りすることは今回は避けることができました。
今までに合格している人がいるテキストをフル活用して一次試験は一発で合格することができました。
アウトプット
暗記するべき内容をインプットできたら過去問を周回することでアウトプットをしていきます。
よく問われる論点が毎年出ているのは他の資格試験と同じかと思います。
毎年出てくる論点は本試験では落としてはいけない問題となりますし、実は同じ箇所だったということもテキストに戻ってみると気付いたりします。
私は、過去問で解けなかった問題の論点をテキストにメモする方法で同じミスを繰り返さない工夫をしていました。
他の資格試験でも同じ方法をとっていましたので、資格試験対策としては有効であると感じています。
終わりに一言
一次試験だけの合格を目指すのであれば難易度はそこまで高いと感じるものではありませんでした。
ただ、科目数が多く、科目間の関連性が低いことを考えると覚える範囲が膨大となるため難しい試験であると感じます。
そして、中小企業診断士の試験が難しいと言われる所以は、一次試験より二次試験にあると思います。
二次試験はまた別の記事で書いてみたいと思います。