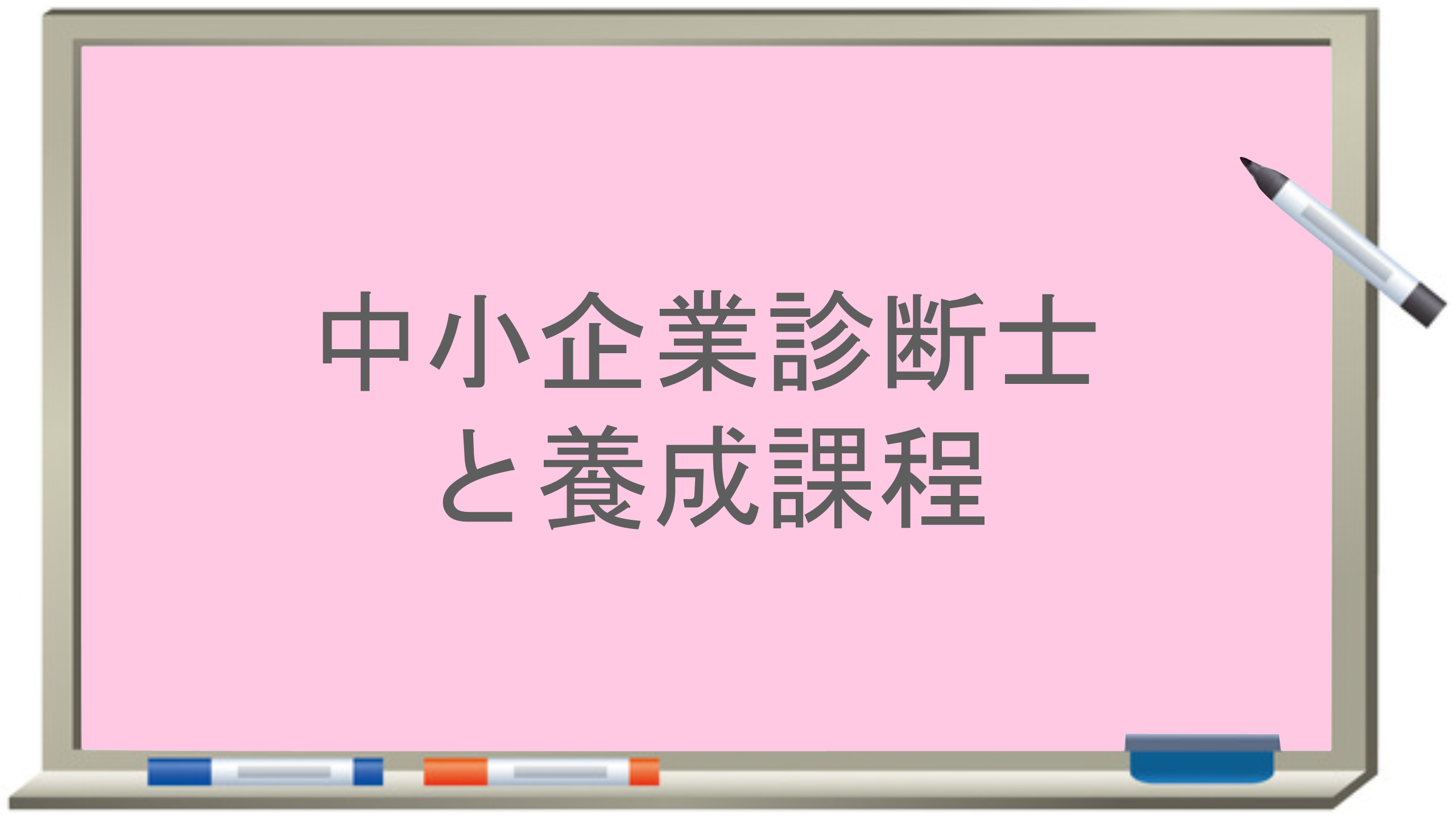東海地方の田舎町で【コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
中小企業診断士の資格と言うと難関という印象がありますが、私もその通りだと思っています。
一般的な勉強時間が1,000~1,200時間ということを考えますと、働きながら合格を目指せる最難関の資格の一つではないかと感じています。
中小企業診断士には試験の合格だけでなく、登録養成課程を修了することで資格を取得できる道がありますので、今回はその養成課程について書いてみたいと思います。
一次試験、二次試験に続く第3回の記事となります。
さて、今回は中小企業診断士の登録養成課程について以下の3点にまとめました。
- 中小企業診断士を名乗れるまで
- 二次試験と養成課程
- 養成課程に通ってみて
中小企業診断士を名乗れるまで
経営に関して一定の知識を持つ
中小企業診断士は、国家資格の一つで経営コンサルタントとなるための唯一の資格となります。
資格がなくても経営コンサルタントを名乗ることはできますので必須ではありませんが、資格があることでの信頼感はあるのではと思います。
名称独占資格ですので、中小企業診断士と名乗るためには資格を保有している必要があります。
経営コンサルタントというだけであれば、中小企業診断士の資格は必要ありません。
名乗るためには試験に合格する必要がありますが、一次試験、二次試験に合格して口述試験に合格しなければなりません。
私が受けてきた試験については別の記事としていますので、そちらをご覧いただければと思います。
一次試験では、経営についての知識を学問的に学んでいきます。マークシート式の試験ですし、科目合格があるので、二次試験に比べると易しいと言えるかもしれません。
二次試験では、実際の事例企業に対して紙面上でコンサルティングを行うことになります。組織人事、マーケティング、製造業、財務会計といったあらかじめ決められた内容を軸にコンサルタントとしてどのような助言ができるかが合否の基準となります。
一次試験、二次試験のどちらも合格できていれば、ある程度の知識は身についているということが証明できる試験内容となっています。
二次試験と養成課程
難易度はどちらも高い
二次試験ではなはく、登録養成課程というものがあることは比較的初期のころから知っていました。
二次試験に合格できなかった人向けの救済制度かなという印象を持っていましたが、よくよく調べていくとどうやらそうではないのではと感じる点が多々あることに気が付きました。
まず、二次試験に合格するためには、4つある事例のすべてが40点以上、かつ総得点で240点以上を獲得する必要があります。
正解が公表されていない試験ですので、過去問をどれだけ解いてもこれが正解というものは分かりません。
私自身も二次試験の対策には時間を割きましたが、試験直前になっても何が正解なのかは分からないままでした。
そして、登録養成課程ですが、受講するために筆記試験と面接があります。他の養成課程は分かりませんが、私が受けたところはありました。
一次試験の内容を理解しているかを確認するための試験ですので、最低限の対策はしておく必要があります。
私は、対策が間違っていたことで試験当日はとても焦りました。
養成課程に通ってみて
知識面と体調面に注意が必要
登録養成課程に通うようになって、世の中にはすごい人がたくさんいるんだなということを知ることができました。
みんなが好き勝手話していることを瞬時にまとめることができる人、財務面にとても強い人、人事面にとても強い人などいろいろな人が受講生として参加されていました。
通わなければ出会うことができなかった立場の人も多くいらっしゃったので、通って正解だったなと感じています。
よい仲間と出会えたことは副次的なメリットですが、メインのメリットであるコンサルタントとしての知識を体系的に学ぶことができたことも私の中ではとても意味があるものでした。
試験勉強だけでは身につかなかった知識や考え方を持った人との意見交換を通じて、本当に多くのこと身につけることができました。
登録養成課程というと、二次試験に合格しなくても中小企業診断士となれる抜け道のような印象をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、私は逆のような印象を持っています。
全員が一次試験に合格している知識を保有している人の集まりで、それぞれの会社では経営層や近しい役職についている人も多くいらっしゃいます。そんな方々とのコミュニケーションをスムーズに行うためには、自分自身もそれなりの知識を保有しておく必要がありますし、みなさんの頭の回転の速さは異常と言えるレベルですのでついていくだけでも必死です。
そして、今回私がやってしまったことですが、体調面の管理も重要な点です。養成課程によっては、健康診断の結果を求められることもあるくらい、体調面は気を付けすぎるということがありません。体調面によりやむなく続けることができなくなることは毎年起きているようです。
終わりに一言
時間や家族が許すのであれば登録養成課程一択だと思っています。
体系的かつ論理的に経営について学べるということは、中小企業診断士となってからも生きてきます。
試験対策では応用できない部分を多く学ぶことができる養成課程をご検討されてみるのもよいかと思います。