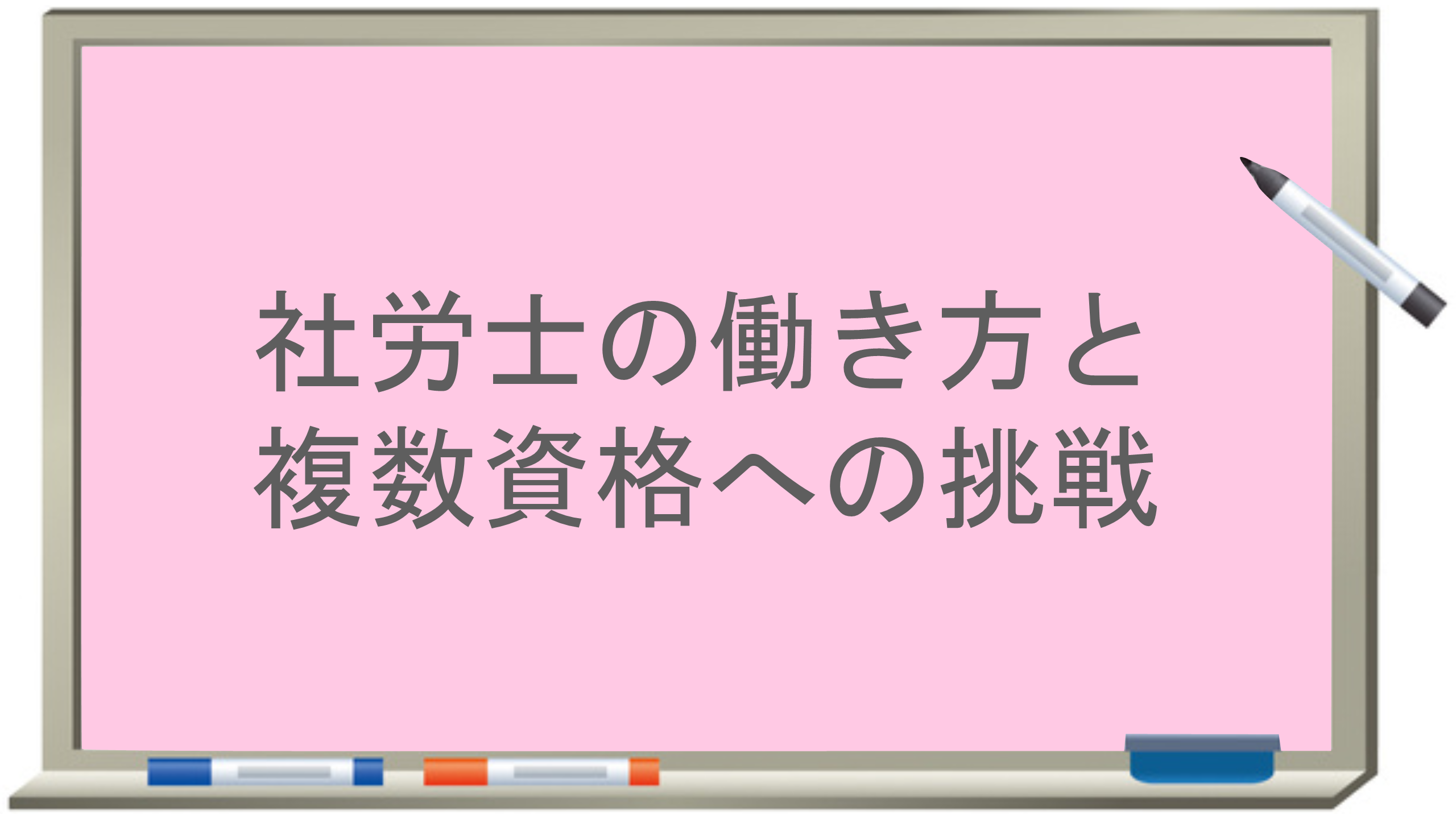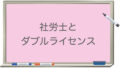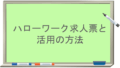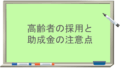東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社労士・コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
最近になって、社労士試験に挑戦したいというお話を耳にします。私自身は受験生支援などは行っていませんので、間接的に耳にする機会がある程度ですが。
年齢にもよりますが、勉強をするのであればぜひとも頑張っていただきたいと応援しています。
さて、今回は私の社労士としての働き方と相性の良い資格の資格について以下の3点にまとめました。
- 社労士としての2年間
- 社労士試験への挑戦
- 相性の良い資格
社労士としての2年間
1年目
過去にも記事にしていますので、重複してしまうかもしれませんが、1年目の社労士としての稼ぎは本当に微々たるものでした。
支部や商工会議所の集まりにも積極的に顔を出したりして、やれることはなんでもやるという考えで活動をしていたのですが、正に貧乏暇なしの状態でした。
そう言った経験からも、開業前には半年分程度の蓄えがあると精神衛生上よいのではと思います。
顧問先もまったく増えず、スポットで依頼を受けた仕事も売上を回収できない有り様でした。
2年目
2年目に入り、少しずつ流れが変わってきた気がします。
1年目に種まきをしておいたところから声をかけていただくことが増え始めたことと、顔を出しておいたところで接点のあった方からご紹介をいただくことが増えました。
ある程度の売上が確保できるようになってからは、仕事を受けるときも余裕を持つことができるようになりました。
初めてやる仕事だとしても、可能な限り調べてやってみるという経験はとても楽しかったです。
顧問先は1年目の終わりくらいから徐々に増え始め、丸2年を過ぎるころには売上が会社員の頃を超えるようにもなりました。スポットの取引先からの仕事や顧問先の就業規則や助成金を支援する機会をもらえることも増えました。
社労士試験への挑戦
始めるなら慎重に
社労士の仕事は事務の代行がメインとなっている先生が多いような気がします。
それ自体を否定するつもりはありませんが、個人的には少し物足りないなと感じています。
元々考えていたように、経営に伴走して、一緒に成長できるようなお手伝いをしているときが楽しいと感じるからでしょうか。
では、今から社労士試験を目指すのはどうなのかと改めて考えてみました。
結論としては、他に資格がなければ、「頑張りましょう」だと考えています。
逆に、他に資格があるのであれば、「よく考えましょう」になります。
理由は2つあります。
一つ目は、社労士の独占業務ではない依頼の比率が高いことです。
税理士さんの税務相談は独占業務ですが(税理士法第2条)、社労士の労務相談は独占業務ではありません。(社会保険労務士法第27条)
社労士法で定められている独占業務は、大きくは事務処理の代行だけとなります。事務屋さんになるのであれば資格が必要ですが、人事労務に強いコンサルタントであれば、難しい資格を持たなくてもなれてしまうということです。
二つ目は、実力が素直に反映されない試験だと感じているからです。
社労士試験の概要は過去にも書いていますし、調べればたくさんの情報がでてきますが、学習が十分であっても選択式の運要素がどうしても避けれません。
一般的に、学習が進んでいる人ほど択一式はよい点が取れると言われいる試験ですが、選択式で足切りになってしまう受験生がたくさんいます。
身近にも選択式で泣かされて何年も挑戦を続けてきた先生が何人もいます。
取り組み始めると、テキスト代や受験料、勉強した時間などの広義のコストがかかりますが、あと1点が諦めきれずに数年間を使ってしまうのはもったいないです。
他に資格があれば、その資格を活かした営業活動に注力した方がよいのかもしれません。
それでも挑戦するというのであれば、サンクコストの損切をどこでするのかをあらかじめ決めておくとよいでしょう。
相性の良い資格
社労士×行政書士×診断士
社会人が独立を目指して資格取得をするのであれば、結果的にこの3つに落ち着くのかなと思います。
どれか一つの資格を持っているだけでも、十分に食べていくことはできると言われていますので、難しい資格試験に挑戦する時間を営業活動に費やす方がよっぽどリターンは大きいです。
学生さんや、専業で勉強をすることができるのであれば、司法試験や司法書士、公認会計士などもっと難易度の高い資格を狙うのもよいかもしれません。
独占業務のないFP2級で独立してうまくいっている経営者の方くを何人も知っていますが、独占業務のある難関国家資格を持っていても長年バイト生活という方も知っています。
つまり、国家資格でないとダメだとか、独占業務がないとダメということはまったくないということです。
今までの社会人経験で培ってきた経験、自分自身の好きなこと、興味の持てる試験内容、これらをどのように組み合わせるかで良い悪いは変わるということです。
終わりに一言
知り合いが社労士を今から狙うと言い出したら、まず一度は止めます。ただ、ゆっくり考えた結果、本当にやりたいのであれば応援します。
受験生支援をしている先生もいますし、私なりのお勧めの勉強法であれば教えることもできます。
気になることがありましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。