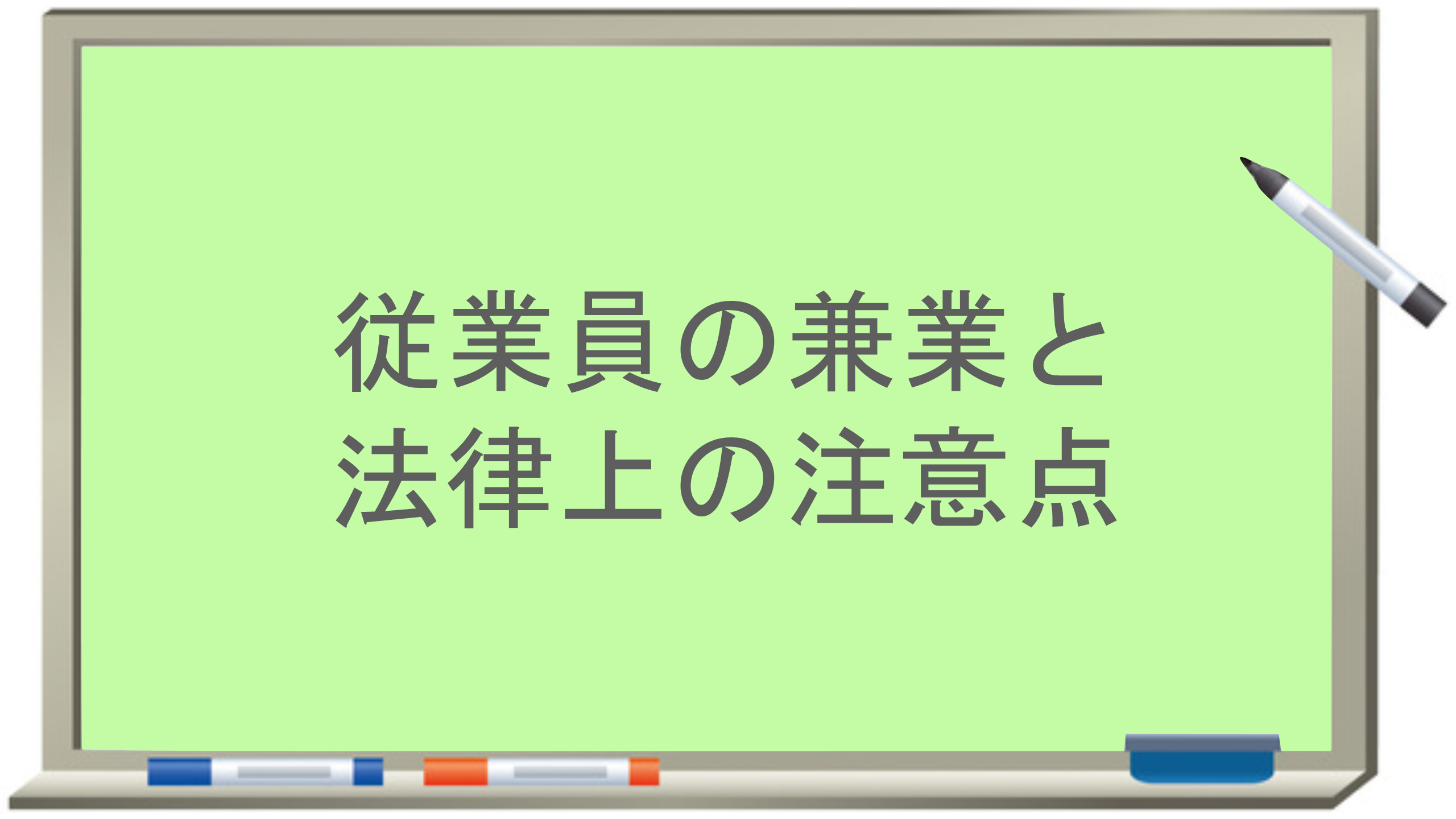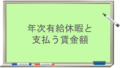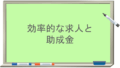東海地方の田舎町で【コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。
働き方の多様化に伴ってか、正社員として働きつつ週末に事業を営む方とお会いする機会も増えてきました。
また、企業の担当者からは、就業規則の作成の際に兼業についての規程を盛り込んでおいてほしいというお話が出てくることもあります。
さて、今回は従業員が副業や兼業をするときの注意点を以下の3点にまとめました。
- 職業は自由に選択できる
- 会社が制限できるのか
- 就業規則や労務管理上の注意
職業は自由に選択できる
職業選択の事由(憲法22条)
学生時代に受けた授業で憲法を学ぶことがありましたが、その中に【職業選択の事由】というものがありました。
有名な条文もありましたし、改めて、今の立場になって調べてみることにしました。
内容を文面通り読みますと、法律で一定の兼業を禁止されている職業についている場合(国家公務員など)を除いて、国民は職業を自由に選ぶことができる権利があると解釈することができます。
ただ、ここで注意しておかなければならないのは、法律が制定されたときというのは、法律ごとに時代背景があるということです。
職業選択の自由は、日本国憲法第22条で定められていますが、この法律が制定されたのは昭和21年だということです。
これは、第二次世界大戦が終戦した翌年となります。
私は当時について詳しく知る世代ではありませんが、今よりも生まれや性別によって選ぶことができる職業に制限があったのではないかということは想像に難くありません。
そんな時代であったからこそ、誰もが自由に職業を選んでもよいということが定められているのです。
今の時代で考えると少し違和感がありますが、それはこの条文に限らず労働基準法でも同様です。
会社が制限できるのか
できるが注意が必要
では、冒頭で相談されたような会社から兼業や副業を制限したいという相談の答えは「できません。」と回答するのが正しいのでしょうか。
個人的な見解にはなりますが、一定の制限は設けることができると考えています。
社労士の試験でも判例は出てきますが、調べてみるとたくさんの判例がでてきます。
それだけ多くの会社で副業や兼業をしたいという声があり、問題が顕在化しているのだなと感じます。
ここで出てくる判例の対象を分類すると大きく以下の3つに分けることができます。
・兼業(本業に近しい分量で事業を行うもの)
・副業(本業の空き時間に行うもの)
・競業避止(同業他社や本業と同業を事業として行うもの)
兼業と副業という言葉に明確な定義付けがあるわけではありませんが、イメージで括弧内のようなものと定義しておきます。
就業規則や労務管理上の注意
就業規則や誓約書を用意する
就業規則には、兼業や副業について書かれているものもありますし、書いてほしいと依頼を受けることもあります。
就業規則に書くだけの場合もあれば、それとは別で入社時に誓約書を締結しているという場合もあります。
就業規則や誓約書で兼業や副業の制限を定めるのであれば、定める目的を明確にした上で、作成する社労士に伝えるとよいでしょう。
よく耳にするお話だと次のようなものがあります。
例)兼業や副業をすることで、
・休息時間が十分でなくなり、本業の業務中の事故につながる
・会社の持つノウハウや営業秘密が外部に漏えいする
・働いている会社によっては自社のイメージを損なう
恐れがあるから制限したい。
労務管理上の注意
就業規則や誓約書で制限をかける場合、対応としては2つに分けられます。
・許可制
・禁止
まず、許可制を選びますと、労務管理において割増賃金の計算が煩雑になります。
基本的には、労働時間は通算されますので、割増賃金の支払いの可能性が出てきます。
これは別の事業主であっても同様です。
そして禁止を選びますと、厳しさについて労働者から訴えを起こされる可能性があります。
前述のような明確な理由を説明できればよいのですが、そうでない場合は正当性について争うことになる可能性もあります。
終わりに一言
兼業を制限する一番の理由は、本業に精一杯頑張ってもらいたいということかと思われます。
それ以外にも、情報漏えいやよく分からないビジネスをすることでの自社のイメージを損なうことが心配になる気持ちも分かります。
他で働かなくても十分な待遇にできるか、納得できる評価制度を作ることも打ち手としては必要かもしれません。
弊所では、従業員が納得できる人事評価制度の制定などのお手伝いも行っております。気になる事業所の方はぜひお気軽にお問い合わせください。